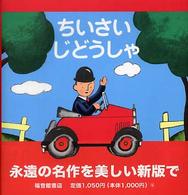目次
第1章 ソ連初期の歴史学と歴史教育
第2章 歴史教育改革の始まり
第3章 「国民史」の模索―ソ連邦史標準教科書の作成
第4章 愛国主義とマルクス主義―独ソ戦前夜のソ連史研究
第5章 独ソ戦と自国史像をめぐる論争
第6章 「ソヴェト愛国主義」の変容と自国史描写の転換
第7章 スターリン最末期のイデオロギー政策と歴史学
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
2
再読。初期ソヴィエト史学史に一定の知識がないと難しい内容かもしれないが、得るところは多い一冊。ロシア帝国から引き継いだ多民族構成と、元々ひとつの国に収まることを前提としていないインターナショナリズムのマルクス主義を国是に、何とかソ連の一国史を立ち上げなければならない。さあどうする?全てが当局のお達しで整然と決められたのかと思いきや、意外に歴史家同士の論争と国際情勢からの影響による紆余曲折、右往左往が続いて一筋縄ではいかない。2021/11/02
DIVERmope
2
ソ連時代前半の歴史教育を、多数の民族が混在するソ連とその国民を統合する手段として論じた著作。歴史とは過去に伸びた政治であり、著作の中で論じられるソ連の歴史教育の変遷とイデオロギーとの関係は、在日朝鮮人を抱えながらも事実上の単一民族国家として機能している現代日本に対して、大きな教訓を残す。北方領土問題はいつから問題視されているのか?なぜそうなったのか?尖閣や竹島の歴史認識とは何か?本書を熟読することで、政治性を帯びた歴史教育、国民の定義と国家組織としての国民統合政策の姿が、より身近なものになるであろう。2013/10/05