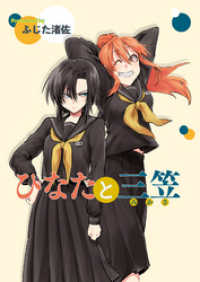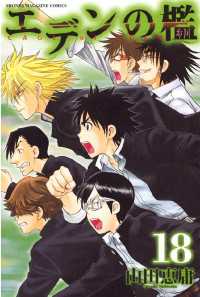内容説明
雅楽とは、日本古来からの上代歌舞、外来の管絃・舞楽、日本の宮廷貴族による催馬楽・朗詠、この三種類の音楽の総称である。美しい装束とともに、これらが醸し出す雅やかな雰囲気は、楽器や歌のどのような演奏から生じるのであろうか。雅楽独特の魅力を探る。
目次
第1章 雅楽への予備知識
第2章 歴史のあらまし(「雅楽」という名称について;外国音楽の流入期(五世紀~八世紀) ほか)
第3章 楽器について(篳篥;横笛;高麗笛・神楽笛 ほか)
第4章 雅楽の各種目(管絃;舞楽 ほか)
第5章 種々の音楽的仕組み(雅楽の音組織;雅楽のリズム ほか)
著者等紹介
増本伎共子[マスモトキクコ]
本名・喜久子。作曲家。桐朋学園大学音楽学部卒業。現在同大学客員教授。1960年代に日本の伝統音楽全般に関するリサーチをこころざし、東洋音楽学会に入会。現在に到る。1970年代以降は作曲活動に専念。作品に、室内歌劇『浅茅ケ宿』、四人の声明家のための『いろは幻想』などがある。日本現代音楽協会、日本作曲家協議会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。