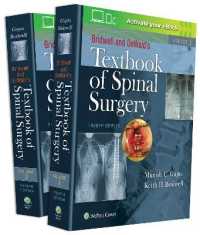出版社内容情報
ブラームスゆかりの地に滞在した著者が、管弦楽作品を徹底分析。ベートーヴェンへの愛情と反発を探求、真のブラームス像に迫る。
弊社刊《ベートーヴェン ピアノ・ソナタ研究》全3冊で打ち立てた方法論に添い、自らもゆかりの地に滞在した作曲家・諸井誠が、ブラームスの管弦楽作品を徹底的に分析、その中に潜むベートーヴェンへの愛情と反発を探求する中で、真のブラームス像に迫る。逝去直前まで校正作業を行っていた著者の絶筆!!
はじめに
序論 ブラームスの協奏曲と交響曲
1. Stufe ニ短調協奏曲とハ短調交響曲
ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15
交響曲第1番 ハ短調 作品68
Capriccio 対立の構図 1 ~処女作と4連作~
2. Stufe ニ長調の交響曲と協奏曲
交響曲第2番 ニ長調 作品73
Capriccio 対立の構図 2 ~はじめとおわり~
ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77
Capriccio 対立の構図 3 ~続はじめとおわり~
3. Stufe 変ロ長調協奏曲からヘ長調交響曲へ
ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 作品83
Capriccio 対立の構図 4 ~《リング》の結末について~
交響曲第3番 ヘ長調 作品90
Capriccio 対立の構図 5 ~R. Wagner, DER TOD IN VENEDIG 1883 ~
4. Stufe ホ短調協奏曲と二重協奏曲~ベートーヴェン離れの調性選択~
交響曲第4番 ホ短調 作品98
Capriccio 対立の構図 6 ~「未来音楽」を巡って~
ヴァイオリン、チェロとオーケストラのための二重協奏曲イ短調 作品102~〈和解の協奏曲〉とは~
まとめ
二重性について
Final Stufe ブラームスの系列複合における調性行脚のことなど
あとがきにかえて
【著者紹介】
東京音楽学校(現東京藝術大学)作曲科卒業。黛敏郎、入野義朗、柴田南雄らと20世紀音楽研究所を組織し、1953年エリザベート王妃国際音楽コンクール作曲部門に第7位、日本人として初の入賞。1957年から65年にかけて軽井沢、東京、大阪等で移動現代音楽祭を開催、十二音音楽、電子音楽等をいち早く取り入れ、60年代から尺八を中心に各種邦楽器の曲やオーケストラと邦楽器を組み合わせた独自のジャンルを開拓、国際的評価を得た。80年代には積極的に音楽評論活動を行い、日本アルバン・ベルク協会を設立、初代会長を務めた。90年代には埼玉県芸術文化振興財団理事長兼芸術監督としてホール企画を推進、2005年からは鎌倉に転じて長年のテーマであるベートーヴェン・ピアノ・ソナタ全曲の分析的研究を行い、音楽之友社からの《ベートーヴェン・ピアノ・ソナタ研究》(全3巻、2010年完成)に結実させた。その後はその手法で、かつてISCM国際現代音楽祭に入選し、レジデンツ・コンポーザーとしてバーデン・バーテンのブラームス・ハウスに滞在したゆかりのブラームスのオーケストラ作品の研究に集中、書き上げた後、逝去された。
内容説明
作曲家・諸井誠の集大成!!1953年、エリザベート王妃国際音楽コンクール作曲部門に日本人として初の入賞を果たし、“竹籟五章”などで第一線の作曲家として活躍、全3巻の“ベートーヴェンピアノ・ソナタ研究”で、独自の分析的楽曲研究方法を打ち立てた諸井誠が、その手法でブラームスのオーケストラ作品を解明した最後の著書!!
目次
序論 ブラームスの協奏曲と交響曲―4つのStufeに分けて捉える
1Stufe ニ短調協奏曲とハ短調交響曲
2Stufe ニ長調の交響曲と協奏曲
3Stufe 変ロ長調協奏曲からヘ長調交響曲へ
4Stufe ホ短調交響曲と二重協奏曲―ベートーヴェン離れの調性選択
final Stufe ブラームスの系列複合における調性行脚のことなど―“ニ短調”から“イ短調”へ
著者等紹介
諸井誠[モロイマコト]
1930年12月17日生れ(東京)。1952年3月東京音楽学校本科(現・東京藝術大学音楽学部)作曲科卒。黛敏郎、入野義朗、柴田南雄等と20世紀音楽研究所を組織し、57年から65年にかけて、軽井沢を中心に、大阪、東京などで移動現代音楽祭を開催。十二音音楽、電子音楽等をいち早く取り入れ、また、1960年代から尺八を中心に各種邦楽器をも手がけ、邦楽器とオーケストラの結合を企図した独自のジャンルを開発するなど、現代音楽における先駆的存在として活躍し、国際的評価を得た(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 設備投資行動の理論