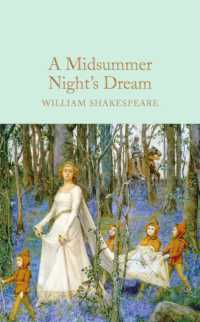出版社内容情報
好評『名曲が語る音楽史』改訂版。「バロック」第1章が新たに書き下ろされ、「現代」の内容が一新。グレゴリオ聖歌からポピュラー音楽までを網羅。
著者紹介:田村和紀夫(タムラワキオ)
尚美学園大学教授。芸術情報学部で西洋音楽史と音楽美学を担当。
目次
第1部 中世とルネサンス(祈りの音楽的形姿―グレゴリオ聖歌の特質と魅力;西洋音楽の始動―中世世界の投影:初期多声音楽;カデンツの成立―デュファイが築いた西洋音楽の基礎)
第2部 バロック(感情表現としての音楽―通奏低音の発生;音楽の「目覚め」―バロックにおける拍子の発見;「海」としてのバッハ―その時代性と超時代性)
第3部 古典派(シンフォニーとソナタの誕生―近代社会と音楽の諸相;古典派の形式原理―“フィガロ”が解き明かす「ソナタ形式」;ミューズの贈り物―モーツァルト的なものを求めて;器楽の最終解答―ベートーヴェンの最後のピアノ・ソナタ)
第4部 ロマン派(“魔王”が開示した世界―ロマン派の表現領域;ロマン派の俯瞰図―ピアノ音楽で辿る19世紀;示導動機と感情表現―“トリスタン”の深層心理;「子守歌」としての芸術―ブラームスのロマンティシズム)
第5部 現代(新しい響きを求めて―調性を超える道;「現代音楽」としてのポピュラー音楽)
著者等紹介
田村和紀夫[タムラワキオ]
1952年、石川県七尾市生まれ。国立音楽大学楽理科を卒業、同大学院修士課程を修了、音楽学を専攻する。現在、尚美学園大学教授。芸術情報学部で西洋音楽史と音楽美学を担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nobi
Wataru Hoshii
ユミセツカヤ
たけぞう
-

- 電子書籍
- お箸を持て!!~実家に帰ったら妖怪たち…
-
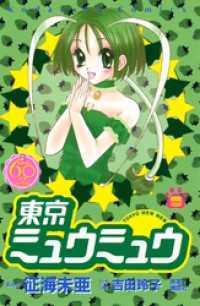
- 電子書籍
- 東京ミュウミュウ なかよし60周年記念…