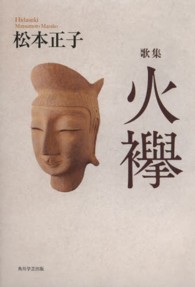出版社内容情報
音楽学習者のバイブル!
本書は、古今東西のあらゆる曲の実例を挙げつつ、交響曲、管弦楽曲、協奏曲などを中心に、作曲の技法を微に入り細に渡って解説した名著である。上下二巻の原著を組み直し、一巻本に。文字はもとより、譜例や図版も最新の方法で書き直し、美しく読みやすくした。
【目 次】
第一編 管絃楽法概論
第一章 汎論
管絃楽法 / 管絃楽の性能 / 聴覚とその錯覚
第二章 組織と編成
組織 / 編成 / 総譜と配置
第二編 楽器各論
第一章 絃楽器群
絃楽器の発音原理 / 絃楽器各論
第二章 木管楽器群
木管楽器の発音原理 / 木管楽器各論
第三章 金管楽器群
金管楽器の発音原理 / 金管楽器各論
第四章 打楽器群
打楽器の発音原理 / 打楽器各論
第五章 編入楽器
<絃を発音体とする楽器>
<簧を発音体とする楽器>
<電気楽器>
<人声>
第三編 管絃楽の共同効果
第一章 器楽観の歴史
第二章 管絃楽法を支配する基礎的な音現象と聴覚機能
I 音の高さに随伴する現象
II 音の強さに随伴する現象
III 音色に随伴する現象
IV 楽器各族の音色特性
1. 木管楽器の音色特性
2. 金管楽器の音色特性
3. 絃楽器の音色特性
4. 打楽器の音色特性
5. 編入楽器の音色特性
V 音の諸要素に関連する現象
音の太さ / 音の量感 / 量感に基づく音色の融和と分離 / 聴覚の選択作用 / 音の方向定位と聴空間(管絃楽の配置) / 聴覚の疲労と倦厭感 巻末に索引
★作曲家・池辺晋一郎氏、推薦の辞
まさに名著中の名著!管絃楽法の本はあまたあれど、これほど精緻かつ実践的なものは他にありません。のみならずこの書は、伊福部昭という稀有な音楽家の厳しさと奥深さ、そして何より「格」に貫かれています。音楽を愛するすべての人に読んでほしい、待望の「完本」です。
【完本 管絃楽法 刊行の経緯】
伊福部昭「管絃楽法」は、1953年9月15日、弊社から原著初版が刊行され、68年1月、大幅な加筆訂正の上、補遺を付した「管絃楽法・上巻」として改めて刊行され、2003年3月の13刷まで版を重ねました。 「下巻」は、1968年3月30日に刊行され、98年の7刷まで版を重ねました。
古今東西のあらゆる音楽理論書、楽譜、楽器製作の理論書、さらには音響学、物理学の原書まで研究された上で上梓されたこの「管絃楽法」は、世界で一番詳細な管絃楽法であるだけでなく、現在でも最新の体系的な管絃楽法です。
活版による原著は上下卷合わせて1500ページを超えていましたが、上下の内容は互いに連関しており、学習者にとっては1巻に収めた方が利便性が高いため、1巻本とし、大判化し段組を2段にして、掲載内容は全く変えずにページ数を減らす方針で2003年より編集にかかりました。
旧漢字は新漢字に直しましたが、内容においては伊福部先生の手が入った原著の記述(上巻13刷、下巻7刷)を重視し、先生独自の語り口を尊重しました。譜例等については、その後の研究の進展によって判明した事実のみ、学習者、研究者のために修正いたしました。
長い編集作業の途中、2006年2月8日、伊福部昭先生が91歳で逝去されました。刊行に際し、先生のご冥福を心からお祈りいたします。
──2008年2月8日 伊福部昭先生の命日に / 音楽之友社
【本書の特色】
1、世界で最も詳細! 現代の楽器まで網羅した管絃楽法です。
ベルリオーズ=R.シュトラウス「管弦楽法」(1905)、W.ピストン「管弦楽法」(1955)など、弊社だけでも別の2冊の定評ある管弦楽法を刊行していますが、伊福部昭先生は原書でそれらの内容を咀嚼した上で、楽器の音色、技法、使用上の留意点にとどまらず、音響効果、聴覚に与える影響、心理的効果まで、およそ作曲者・編曲者がわきまえなければならないすべての点に具体的な回答を与えています。また1968年時点での内容が盛り込まれているため、現代の楽器、民族楽器、打楽器についても述べられており、現時点で世界で最も使いやすい管絃楽法となっています。
2、著者ご本人と東京芸大、東京音大などの後継者が結集して編集。
2003年からの編纂作業は、当初伊福部先生ご自身が当たられ、ご逝去された後は松村禎三先生、今井重幸先生をはじめ、伊福部先生の薫陶を受けた方々が結集して編集に当たりました。編集者並びに協力者は39名の皆様です。譜例については、旧版の編纂された時代はまだ作曲家の原資料が乏しかった時代であったため、改めて原典に当たり、確認しつつ必要な部分は改めました。
3、譜例・図版1005点、索引項目約5000項目
圧倒的な資料を収載しています。全楽器の音域の譜例、移調楽器の記譜と実際の音の譜例はすべて掲載されています。曲の譜例は古典から現代まで含まれていますが、色彩感があるマーラー、ドビュッシー、ラヴェル、ファリャ、ストラヴィンスキーなどの引用が多く見られます。索引項目は旧版上下の項目を必須とし、編集委員が若干追加をいたしました。辞典以外の書物では空前の索引項目です(弊社比較)。
4、見やすくしつつ、伊福部先生の「姿」が見える本をめざしました。
旧版A4サイズを拡大し2段組に。テキストはもちろん、図版・譜例もすべて最新の方法で書き改めました。他方、文章については、池部晋一郎先生が推薦文も触れている独特の品格を尊重し、新漢字を使いながらも言葉遣いは旧版を尊重しました。
<編集委員会>
今井重幸、松村禎三、池野成、三木稔、真鍋理一郎、永瀬博彦、小久保淳子、藤原豊、前川健彦、和田薫、加賀美江、石丸基司、今井聡、甲斐由美子、堀井智則
<協力者>
伊福部玲子、安倍姜子、伊福部極、伊福部達、有馬礼子、甲田潤、澤田かおる
浅利勇児、井上誠、岩崎奈菜、岩田晏実、草野恵子、哘崎考宏、田中祐香子、出口寛泰、徳島勝幸、豊田朋久、新里真澄、林明子、福田滋、松本敏晃、八尋健生
内容説明
第一編には、管絃楽の全般的性能に関する基礎的な概論、第二編には管絃楽を構成する個々の楽器の性能、即ち楽器各論が述べられる。楽器相互間の連関性と其の共同効果に関しては、三編に述べられる。
目次
第1編 管絃楽法概論(汎論;組織と編成)
第2編 楽器各論(絃楽器群;木管楽器群;金管楽器群;打楽器群;編入楽器)
第3編 管絃楽の共同効果(器楽観の歴史;管絃楽法を支配する基礎的な音現象と聴覚機能)
著者等紹介
伊福部昭[イフクベアキラ]
1914年北海道釧路に生まれる。北海道大学卒業。独学で作曲を学び、1935年「日本狂詩曲」でチェレプニン賞第一位、1943年「交響譚詩」でビクター管弦曲懸賞第一位・文部大臣賞を受賞。日本民族の感性を基調にした、土俗的で叙情的な作風で知られる。東京藝術大学、東京音楽大学で教鞭を執り、芥川也寸志、黛敏郎、石井眞木ら多くの作曲家を育てた。2003年度文化功労者顕彰、紫綬褒章、勲三等瑞宝章、従四位銀杯三号下賜等。2006年没。主要作品:日本組曲、日本狂詩曲、土俗的三連画、交響譚詩、シンフォニア・タプカーラ、ヴァイオリン協奏曲第1番/第2番、ラウダ・コンチェルタータ、交響的エグログ、リトミカ・オスティナータ、サロメ、アイヌの叙事詩に依る対話体牧歌、琵琶行(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
shostakovich
kzmt
もよ