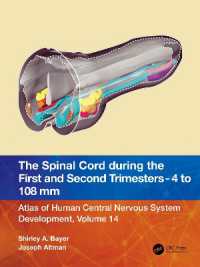内容説明
貨幣とは何か、貨幣はいかにして発生し、いかなる性質をもつのか、ということは、市場の発生以来絶えず問題にされてきた。現代の貨幣をめぐっても、内生説と外生説の対立など、根本的な所で貨幣の性格について、したがってその貨幣の管理をめぐっても、まったく異なる見解が併存している。内生説を唱えるのはケインジアンであり、外生説はフリードマン等のマネタリストである。前者は、一九世紀半ばの銀行学派の見解に源流をもち、また後者は、貨幣数量説を基盤とする通貨学派の現代版ともみられるが、伝統的な貨幣論争が、時代状況を異にして新たな理論構成を加えながらも、延々と継続しているともいえるのである。このような貨幣論争についての検討は、貨幣論の研究に欠かせない意味をもっていると思われる。本書では、こうした貨幣論争への回答を意識しながら検討を進めていく。
目次
第1編 信用と貨幣(金属流通と紙券流通;信用創造のメカニズム;銀行間組織の重層的構造と信用貨幣 ほか)
第2編 貨幣信用学説(スミスの信用論;リカードウの信用論なき貨幣論;通貨論争 ほか)