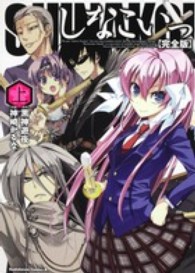内容説明
生活の安定を目指して、人々は自然界を支配する神に祈りを捧げ、それを形にしようとさまざまな祭祀を創出してきた。豊穣祭祀や除厄祭祀などである。そうした祭祀には、神への感謝の意が、モノとして明確に示されねばならなかった。人々は神への供物を用意し、代わりにその恩恵に預かろうとしたのである。
目次
本編 日本における動物供犠の位置(動物供犠の系譜―野獣と家畜;中国大陸の動物供犠―黄河文明と長江文明;朝鮮半島の動物供犠―大陸と列島の架け橋;日本列島の動物供犠―血とオビシャ・卜骨;生贄・胙・祝―動物供犠の用語的検討;狩猟・農耕と供犠―縄文的祭祀から弥生的供犠へ;農耕と家畜の供犠―大陸・半島的供犠の移入;総括と展望―人身御供・人柱と首狩り)
付編 日本古代の動物供犠と殺生の否定(古代における動物供犠と殺生禁断;古代における殺生罪業観と狩猟・漁撈)
著者等紹介
原田信男[ハラダノブオ]
1949年栃木県生まれ。1974年明治大学文学部卒業。1983年明治大学大学院博士後期課程退学。1987年札幌大学女子短期大学部専任講師に就任、2002年からは国士舘大学21世紀アジア学部教授。専攻:日本文化論・日本生活文化史。著書に『江戸の料理史』(中公新書、1989年、サントリー学芸賞受賞)、『歴史のなかの米と肉』(平凡社選書、1993年、小泉八雲賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 和書
- 夢見るおすましやさん