- ホーム
- > 和書
- > 理学
- > 環境
- > 資源・エネルギー問題
内容説明
「今、日本が選ぶべき発電方法、エネルギー戦略は何か?」という疑問への答えを、読者自らが出すための情報と知識を、多面的な観点から提供。
目次
プロローグ エネルギーをみるときに必要な視点は?
第1章 火力発電は本当に“悪者”なのか?
第2章 水力発電の潜在ポテンシャルを有効活用しよう
第3章 「火山大国」日本で地熱発電の開発が遅れている理由
第4章 風力と太陽光発電の普及には等身大の評価が重要
第5章 開発が期待される次世代の自然エネルギー
第6章 その場しのぎの省エネから構造の省エネへ
第7章 一次エネルギーから考えなければ本質はわからない
第8章 自然エネルギーを正しく普及させるために
第9章 日本のエネルギーのベストミックスは?
エピローグ エネルギーの未来を目指す噛みあう議論のために
著者等紹介
石川憲二[イシカワケンジ]
科学技術ジャーナリスト、作家。1958年、東京生まれ。東京理科大学理学部卒業。週刊誌記者を経てフリーランスの編集者&ライターに。書籍や雑誌の制作および小説の執筆を行っているほか、25年以上にわたって企業を取材し、技術とビジネスに関する解説記事を書き続けている。扱ってきた科学技術領域は、電気・電子、機械、航空・宇宙、デバイス、材料、化学、光学、コンピュータ、システム、通信、ロボット、エネルギーなど(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とうゆ
9
レポートの資料として再読。やはりこれからの電力エネルギーの鍵は、省エネと石炭を用いた火力発電のさらなる技術向上だと再認識した。2014/06/01
とうゆ
7
著者は省エネルギーにより消費電力の伸び率をマイナスにすることを押しているが、それには無理があると思う。いくら日本の人口が減るとはいっても、電気自動車を始め身の回りの電子化はもはや当然の流れになっている。もちろん省エネの努力はすべきだが、消費電力を大幅に減らすのは難しいだろう。しかし火力の高効率化や地熱発電のさらなる開発の話には希望が持てた。やはり電気エネルギー問題には抜本的な解決策などなく、地道な技術開発や省エネにより少しづつ状況を改善していくしかないのだろう。2014/05/20
えふ
1
とりあえず、これまでは国防や外交と並んで国策として扱われてきたエネルギー問題が、地方レベルで取り組まなければいけない問題になってきているんだな、ということは分かりました。水力、太陽熱、地熱発電を頑張ればエネルギー問題は何とかなるんじゃないかと思っていたけど、どうにもならないらしい。水力が小規模発電では予想外に非力。太陽光の実勢発電量がメーカー公称値の一割程度しかないというのも予想外。そんなに低いのか、と。省エネ機器を取り入れるよりも、エネルギーを使わない生活を考えよう、というのはその通りだと思う。2013/10/04
レミー
0
エネルギーに関する誤解を修正すること、これからのエネルギーの在り方と使い方を個人が考えることの重要性を認識。火力発電の発展、原発の在り方、地熱などのマイナーエネルギー、そして新しいエネルギーあたりが鍵となるのではないだろうか。感情的にエネルギー問題を語る光景が見受けられるが、それよりもどう変わるかを考えた方が有益ではないか。政府が機能していないという残念な一面が本書に述べられていたし、事実ではないか。文理にとらわれた教育により、知識に偏りが生じその結果かもしれないと、教育の観点からも考えさせられた。2015/12/30
じじ
0
興味があった太陽光の部分だけ読んだ。 10年近く前の本なので今とはかなり違う部分もあるだろう。専門家が読むには不向き。 私のような専門外の人間には、基本的な考え方の部分だけ拾い集めるような形で読むことができた。根拠として細かい計算式も随所に見られるけど、読み飛ばしながらでも言いたいことは伝わってきた。2019/12/15
-
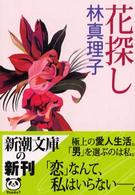
- 和書
- 花探し 新潮文庫







