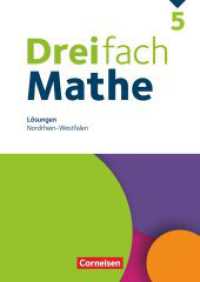出版社内容情報
【セールスポイント】
TCP/IPの最新の情報を、中・上級者向けにくわしく紹介。
【発刊の目的と内容】
TCP/IPは、現在最も広く普及しているインターネットのプロトコルである。
本書は、このTCP/IPの各プロトコルについて、くわしく紹介した解説書、「TCP/IP Explained」(Philip Miller著 Digital Press発行」を翻訳したもの。
マスタリングTCP/IP 入門編をマスターした読者が、各プロトコルのもっと詳しいメカニズムを学ぶのに適した内容となっている。
【購読対象者】
インターネット関連技術者
システム管理者
システムインテグレータ
【詳細目次】
第1章 TCP/IPとインターネット
1.1 ネットワークの仕組み
1.2 TCP/IPとは
1.2.1 TCP/IPの簡単な歴史
1.2.2 インターネットプロトコルセット
1.3 インターネット
1.3.1 インターネットの成長
1.4 まとめ
第2章 TCP/IPでの標準化
2.1 標準化
2.2 Internet Architecture Board
2.2.1 Internet Engineering Task Force
2.2.2 Internet Research Task Force
2.3 インターネットプロトコル標準
2.3.1 プロトコルの位置付け
2.3.2 プロトコルの格付け
2.3.3 RFC(Request For Comments)
2.4 インターネットプロトコルのアーキテクチャ
2.4.1 OSI参照モデル
2.4.2 OSIモデルとLAN
2.4.3 インターネットプロトコルセットモデル
2.5 主要なアーキテクチャの比較
2.6 まとめ
第3章 ネットワーク技術と中継システム
3.1 LAN、WAN技術とインターネットワーキング
3.2 イーサネットとIEEE 802.3
3.2.1 802.3仕様
3.2.2 イーサネットと802.3のフレーム構造
3.2.3 イーサネット/802.3の動作
3.3 トークンリング
3.3.1 802.5の仕様
3.3.2 802.5のフレーム構造
3.3.3 802.5の動作
3.4 FDDI
3.4.1 FDDIの仕様
3.4.2 FDDIのフレーム構造
3.4.3 FDDIの動作
3.5 中継システム
3.5.1 リピータ
3.5.2 ブリッジ
3.6 WANのリンク
3.7 まとめ
第4章 インターネットのアドレス
4.1 インターネットアドレスとその問題点
4.2 アドレス体系の必要性
4.3 インターネットのアドレス
4.3.1 ドット付き10進表記
4.3.2 IPアドレスの識別と規則
4.3.3 適切なアドレス体系の選択
4.3.4 フリーアドレス
4.4 ルーティングの基本
4.5 MACアドレスの解決
4.5.1 ARP(Address Resolution Protocol)
4.5.2 ARPプロトコルのフォーマット
4.5.3 アドレス解決における問題点
4.5.4 非ブロードキャストネットワーク用のアドレス解決
4.6 RARP
4.7 サブネット
4.7.1 本性的サブネットマスク
4.7.2 サブネットマスクの入手
4.7.3 サブネットマスクを使うにあたっての指針
4.8 マルチホーミング
4.9 単一物理接続に対する複数IPアドレスの割り当て
4.10 今後のインターネットアドレス体系
4.11 まとめ
第5章 IP(Internet Protocol)
5.1 IPの2つの基本機能
5.2 IPデータグラム
5.3 IPデータグラムのオプション
5.3.1 オプションリスト終了
5.3.2 無操作
5.3.3 セキュリティ
5.3.4 ルーズソースルーティングとストリクトソースルーティング
5.3.5 ルートレコード
5.3.6 インターネットタイムスタンプ
5.4 データグラムのフラグメント化
5.5 まとめ
第6章 ICMP(Internet Control Message Protocol)
6.1 ICMPの役割
6.2 ICMPメッセージのタイプ
6.2.1 ICMP宛先到達不能メッセージ
6.2.2 ICMP時間超過メッセージ
6.2.3 ICMPパラメータ異常メッセージ
6.2.4 ICMP発信抑制メッセージ
6.2.5 ICMPルート変更メッセージ
6.2.6 ICMPエコー要求メッセージ/ICMP応答メッセージ
6.2.7 ICMPタイムスタンプ要求メッセージ/ICMPタイムスタンプ応答メッセージ
6.2.8 ICMP情報要求メッセージ/ICMP情報応答メッセージ
6.2.9 ICMPアドレスマスク要求メッセージ/ICMPアドレスマスク応答メッセージ
6.3 ICMPの拡張機能
6.3.1 ルーター発見
6.4 まとめ
第7章 TCP(Transmission Control Protocol)
7.1 TCPの役割
7.2 TCPの動作
7.2.1 基本的なデータ転送
7.2.2 信頼性
7.2.3 フロー制御
7.2.4 多重化
7.2.5 コネクション
7.3 TCPセグメントヘッダ
7.4 TCPオプション
7.5 コネクション管理
7.5.1 コネクション確立
7.5.2 コネクション維持
7.5.3 コネクション終了
7.5.4 TCPの状態遷移
7.6 まとめ
第8章 UDP(User Datagram Protocol)
8.1 UDPの機能と長所
8.2 UDP多重化
8.3 UDPデータグラムのヘッダ
8.3.1 UDPとICMP
8.4 まとめ
第9章 ルーティングの原理
9.1 ルーティングの機能と役割
9.2 直接ルーティングと間接ルーティング
9.2.1 ルーティングプロトコル
9.2.2 スタティックルートとデフォルトルート
9.3 ルーティングとサブネットマスク
9.3.1 可変長サブネットマスク
9.4 ARPとサブネット環境
9.3.1 Proxy ARP
9.5 まとめ
第10章 RIP(Routing Information Protocol)
10.1 RIPの機能と役割
10.2 ルートの品質の尺度
10.3 RIPプロトコルの実行
10.3.1 トポロジーの変更の処理
10.3.2 スプリットホライズン
10.3.3 ポイズンリバース
10.3.4 トリガー式更新法
10.3.5 ルート情報の状態とタイマー
10.4 RIPプロトコルのフォーマットと動作
10.4.1 RIPデータグラムの処理
10.4.2 起動時のルーターの動作
10.5 RIPをめぐる議論
10.5.1 RIPの制限
10.5.2 RIPの利点
10.6 RIP2
10.6.1 RIP2プロトコルのフォーマット
10.6.2 RIP2の認証機構
10.6.3 RIP2とマルチキャスティング
10.6.4 RIP1との互換性
10.7 まとめ
第11章 OSPF(Open Shortest Path First)
11.1 OSPFの機能と役割
11.2 メトリック
11.2.1 TOSルーティング
11.2.2 同一コストのパス
11.3 OSPFの概要
11.3.1 OSPFの用語
11.3.2 ネットワークとエリアのタイプ
11.3.3 指名ルーターとバックアップ指名ルーター
11.3.4 ルーターの隣接関係とネットワークタイプ
11.4 プロトコルの動作
11.4.1 Helloプロトコル
11.4.2 データベース情報の交換と隣接関係の成立
11.4.3 データベース記述パケットの交換
11.4.4 リンク状態要求(LSR)による追加情報の要求
11.4.5 リンク状態更新パケット
11.4.6 リンク状態広告
11.5 最短パスツリー(Shortest Path Tree)の作成
11.5.1 ルーティングテーブル
11.6 エリアの使い方
11.6.1 バックボーンエリア
11.6.2 仮想リンク
11.6.3 エリア内ルーティングとエリア間ルーティング
11.7 自律システムの結合
11.8 まとめ
第12章 EGP(Exterior Gateway Protocol)
12.1 EGPの機能と役割
12.2 EGPプロトコルのフォーマットと動作
12.2.1 EGPメッセージヘッダ
12.2.2 隣接装置獲得/中止
12.2.3 隣接装置到達性
12.2.4 ポーリングコマンド
12.2.5 更新応答/指示メッセージ
12.2.6 エラー応答/指示
12.3 EGPメトリック
12.4 EGPの状態遷移
12.5 EGPの例
12.6 まとめ
第13章 BGP(Border Gateway Protocol)
13.1 BGPの機能と役割
13.2 BGPの動作
13.3 BGPメッセージフォーマット
13.3.1 BGPメッセージヘッダ
13.3.2 オープンメッセージ
13.3.3 更新メッセージ
13.3.4 KeepAliveメッセージ
13.3.5 通知メッセージ
13.4 簡単なBGPの例
13.5 まとめ
第14章 IPでのブロードキャストとマルチキャスト
14.1 複数のホストに同時に情報を伝える
14.2 ブロードキャスト
14.1.1 サブネットがある場合のブロードキャスト
14.3 マルチキャスト
14.3.1 ホストグループのアドレス
14.3.2 IPマルチキャストからローカルネットワークマルチキャストへのマッピング
14.4 IGMP(Internet Group Management Protocol)
14.4.1 IGMPの動作
14.4.2 ホストグループアドレスの割り当て
14.5 マルチキャストルーティング情報の伝達
14.6 DVMRP(Distance Vector Multicast Routing Protocol)
14.5.1 DVMRPの動作
14.7 マルチキャストOSPF(MOSPF: Multicast OSPF)
14.7.1 MOSPFの動作
14.7.2 簡略化最短パスツリー(Pruned Shortest Path Tree)
14.8 まとめ
第15章 DNS(Domain Name System)
15.1 DNSの機能と役割
15.2 ドメイン名スペース(Domain Name Space)
15.2.1 別名(エイリアス)
15.2.2 インターネットメールシステムとDNS
15.3 リソースレコード
15.3.1 A(アドレス)タイプリソースレコード
15.3.2 Cname(Canonical Name、標準名)タイプリソースレコード
15.3.3 Hinfo(Host Information、ホスト情報)タイプリソースレコード
15.3.4 MB、MD、MF、MG、Minfo、MR、およびMX(Mail、メール)タイプリソースレコード
15.3.5 NS(ネームサーバー)タイプリソースレコード
15.3.6 PTR(Pointer、ポインタ)タイプリソースレコード
15.3.7 SOA(Start of Authority、オーソリティ開始位置)タイプリソースレコード
15.3.8 TXT(テキスト)タイプリソースレコード
15.3.9 WKS(ウェルノウンサービス)タイプリソースレコー
ド
15.3.10 NULLタイプリソースレコード
15.4 DNSの動作
15.4.1 ネームサーバーの動作
15.5 DNSプロトコルのフォーマット
15.5.1 ヘッダセクション
15.5.2 質問セクション
15.5.3 回答、オーソリティ、および追加情報の各セクショ
ン
15.5.4 メッセージの圧縮
15.6 逆問い合わせ
15.7 DNS情報の検索
15.8 DNSの例
15.9 まとめ
第16章 TelnetとRlogin
16.1 ホストへのオンラインアクセス
16.2 Telnetプロトコル
16.2.1 オプションコマンドと応答
16.2.2 Telnetの制御機能
16.2.3 標準NVT文字
16.2.4 Telnetのコマンドとオプション
16.2.5 Telnetオプションに関するRFC
16.2.6 Telnetセッションの例
16.3 Rlogin
16.3.1 Rloginのコマンド
16.3.2 Rloginでのセキュリティへの配慮
16.4 まとめ
第17章 FTP(File Transfer Protocol)
17.1 FTPの機能と役割
17.2 FTPの基本動作
17.3 データ転送機能
17.3.1 データタイプ
17.3.2 データ構造
17.4 FTP転送モード
17.4.1 ストリームモード
17.4.2 ブロックモード
17.4.3 圧縮モード
17.5 ファイル転送機能
17.5.1 アクセス制御コマンド
17.5.2 転送パラメータ
17.5.3 FTPサービスコマンド
17.6 FTP応答
17.7 完結したFTPの例
17.8 まとめ
第18章 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
18.1 インターネットでのメール配信
18.2 送信装置と受信装置の決定
18.3 メールメッセージの送信
18.3.1 検証と拡張
18.4 SMTPコマンドと応答
18.4.1 SMTPコマンド
18.4.2 SMTP応答
18.4.3 送信側へのメール返送
18.5 メッセージのヘッダフォーマット
18.6 まとめ
第19章 BootPとTFTPによるインターネットホストの起動
19.1 BootPとTFTPの機能と役割
19.2 BootP(Bootstrap Protocol)
19.2.1 BootPの基本動作
19.2.2 BootPプロトコルのフォーマット
19.2.3 BootP要求の作成
19.2.4 ルーターでのBootPの使用
19.2.5 BootPの設定
19.2.6 BootP要求の再送信
19.3 TFTP(Trivial File Transfer Protocol)
19.3.1 TFTPの動作
19.3.2 TFTPのプロトコルフォーマット
19.3.3 UDPポート番号の決定
19.3.4 セキュリティとTFTP
19.3.5 TFTPのサンプルパケットトレース
19.3.6 Directed TFTP
19.4 まとめ
第20章 SNMP(Simple Network Management Protocol)
20.1 SNMPの機能と役割
20.2 管理タスクとSNMP
20.3 SNMPの構造
20.4 SMI
20.5 MIB
20.5.1 他のMIBに関するRFC
20.6 SNMP
20.6.1 認証
20.6.2 SNMPプロトコルのフォーマット
20.7 SNMPの例
20.8 Remote Monitoring MIB(RMON)
20.9 SNMPの将来
20.10 まとめ
第21章 その他のプロトコル
21.1 各種のプロトコル
21.2 Echo Protocol
21.3 Discard Protocol
21.4 Time Protocol
21.5 Daytime Protocol
21.6 Network Time Protocol(NTP)
21.7 Line Printer Daemon Protocol(LPD)
21.8 SYSLOG
21.9 Finger
21.10 WHOIS/nickname
21.11 Character Generator Protocol(CHARGEN)
21.12 Quote of the Day(Quote)
21.13 Users
21.14 まとめ
第22章 WAN上での通信
22.1 SLIPとPPP
22.2 SLIP(Serial Line IP)
22.2.1 SLIPのカプセル化
22.2.2 SLIPパケットのサイズ
22.3 圧縮
22.3.1 Van Jacobson圧縮
22.4 PPP(Point - to - Point Protocol)
22.4.1 PPPのカプセル化
22.4.2 PPPリンクの動作
22.4.3 リンク制御プロトコル(LCP)パケットの一般的なフォーマット
22.4.4 LCP設定要求
22.4.5 LCP設定に対する応答確認と拒絶
22.4.6 LCP終了要求と終了Ack
22.4.7 LCPコード拒絶
22.4.8 LCPプロトコル拒絶
22.4.9 LCPエコー要求/応答
22.4.10 LCP廃棄要求
22.4.11 LCP識別
22.4.12 LCP残存時間
22.4.13 PPP設定の例
22.5 PPP認証プロトコル
22.5.1 パスワード認証プロトコル(PAP)
22.5.2 チャレンジハンドシェーク認証プロトコル(CHAP)
22.6 PPPリンク品質監視(LQM)
22.6.1 LQM設定オプション
22.6.2 リンク品質報告
22.6.3 リンクの品質評価
22.7 マルチリンクプロトコル
22.7.1 マルチリンクの動作
22.8 IP制御プロトコル(IPCP)
22.8.1 IPCP設定オプション
22.8.2 PPPでのVan Jacobson圧縮
22.9 シリアルリンクでのPPPフレーム化
22.9.1 データ透過性の保持
22.9.2 HDLC方式フレームを使うPPPの例
22.10 まとめ
第23章 安全なインターネット環境の構築
23.1 インターネットのセキュリティ
23.2 セキュリティとプロトコル
23.2.1 データリンク層プロトコル
23.2.2 トランスポートプロトコル
23.2.3 管理プロトコルと情報プロトコル
23.2.4 ルーティングプロトコル
23.2.5 アプリケーションプロトコル
23.3 セキュリティフィルタの設計
23.3.1 Telnetのフィルタ
23.3.2 SMTPのフィルタ
23.3.3 FTPのフィルタ
23.3.4 DNSのフィルタ
23.3.5 ICMPのフィルタ
23.3.6 SNMPのフィルタと管理
23.4 フィルタのタイプ
23.4.1 IPのフラグメント化とSYNフラグ
23.5 その他の問題
23.5.1 無許可のルーター
23.5.2 ダイヤルインアクセス
23.6 まとめ
第24章 IPバージョン6
24.1 IPバージョン6とは
24.2 IPバージョン6の拡張機能
24.3 IPv6のアドレス体系
24.3.1 バージョン6アドレスの表示
24.3.2 ユニキャストアドレス
24.3.3 バージョン6アドレスへのバージョン4アドレスの埋め込み
24.3.4 プロバイダ方式グローバルユニキャストアドレス
24.3.5 ローカル使用IPv6ユニキャストアドレス
24.3.6 エニィキャストアドレス
24.3.7 マルチキャストアドレス
24.4 IPバージョン6ヘッダのフォーマット
24.5 拡張ヘッダ
24.5.1 オプション
24.5.2 ホップバイホップオプションヘッダ
24.5.3 ルーティングヘッダ
24.5.4 フラグメントヘッダ
24.5.5 宛先オプションヘッダ
24.5.6 次ヘッダがない場合
24.6 IPバージョン6とICMP
24.6.1 宛先到達不能
24.6.2 パケット過大メッセージ
24.6.3 時間超過メッセージ
24.6.4 パラメータ異常メッセージ
24.6.5 エコー要求メッセージとエコー応答メッセージ
24.6.6 グループメンバーシップメッセージ
24.6 まとめ
付録A ネットワーク用語集
付録B 公式インターネットプロトコル標準(RFC2200)
付B.1 標準プロトコル
付B.2 ネットワーク固有標準プロトコル
付B.3 草案標準プロトコル
付B.4 提案標準プロトコル
付B.5 実験プロトコル
付B.6 参考プロトコル
付B.7 歴史的プロトコル
付録C 管理情報ベースMIB II(RFC1213)
付C.1 systemグループ
付C.2 interfacesグループ
C.2.1 ifTable
付C.3 atグループ
付C.4 ipグループ
C.4.1 IPアドレステーブル
C.4.2 IPルーティングテーブル
C.4.3 IPアドレス変換テーブル
付C.5 icmpグループ
付C.6 tcpグループ
C.6.1 TCPコネクションテーブル
付C.7 udpグループ
C.7.1 UDPリスナーテーブル
付C.8 egpグループ
C.8.1 EGP隣接装置テーブル
付C.9 transmissionグループ
付C.10 snmpグループ
付録D 参考文献
付D.1 RFC
付D.2 その他の参考文献
索引
内容説明
TCP/IPのメカニズムについてくわしく紹介した決定版。
目次
TCP/IPとインターネット
TCP/IPでの標準化
ネットワーク技術と中継システム
インターネットのアドレス
IP(Internet Protocol)
ICMP(Internet Control Message Protocol)
TCP(Transmission Control Protocol)
UDP(User Datagram Protocol)
ルーティングの原理
RIP(Routing Information Protocol)〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
マメラッティ
ふぁしゅー
ますみ
JP7FKF
myknek