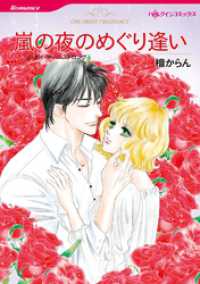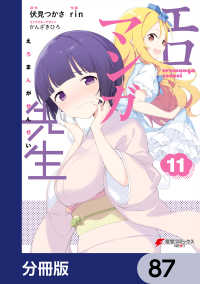出版社内容情報
【セールスポイント】
楽しみながら学ぶ天文学 内容充実のCD-ROM付き!
【発刊の目的と内容】
天文学の楽しさを感じながら読むことができる天文学の入門書。
著者前作「星空ウォッチングのすすめ」にやや高度な内容を盛り込み、さらに星座の位置や天文運動を学べる付録CD-ROMを添付。立体的、多角的に天文学を学ぶことができる。
【購読対象者】
天文学に興味のある学生・一般
【付録】
Windows版CD-ROM付き。
【詳細目次】
はじめに
口 絵
第1章 星座物語
第2章 星の世界への招待
2.1 天の座標系-歳差運動・星座名
2.1.1 星座と星
2.1.2 春分点
2.2 星のエネルギー-物理諸量
2.2.1 絶対等級
2.2.2 分光型(スペクトル型)・温度・半径
2.2.3 ヘルツシュプリンク・ラッセル(HR)図
2.2.4 星のエネルギー源
2.3 近隣の星たち-赤白の矮星
2.3.1 赤い小人星
2.3.2 シリウス
2.4 星のゆりかご-若き星雲星団
2.4.1 オリオン星雲
2.4.2 星団星雲
2.5 めぐる双子星-連星
2.5.1 互いに互いの周りを回る星
2.5.2 さまざまな三重連星
2.5.3 四重連星・六重連星
2.5.4 巨漢同士,小人同士
2.6 点滅激変-変光星
2.6.1 変光星
2.6.2 新星
2.6.3 最も明るい(?)星
2.7 見つかった惑星系
2.8 星々の黄昏-球状星団・惑星状星雲
2.8.1 老いた集団
2.8.2 華麗な最終コマ
2.9 最後の爆発-超新星・パルサー
2.9.1 超新星
2.9.2 パルサー-この精巧な宇宙時計
2.10 死してなお活動-ブラックホール
2.10.1 黒い白鳥
2.10.2 X線星
2.10.3 近接連星の運命
2.11 銀河の外へ-銀河とクェーサー
2.11.1 銀河のいろいろ
2.11.2 銀河団
2.11.3 クェーサー
第3章 惑星運動
3.1 わが太陽系のメンバー
3.1.1 惑星の発見
3.1.2 惑星の諸性質
3.1.3 チチウス・ボーデの法則
3.1.4 彗星について
3.2 惑星軌道運動
3.2.1 時制について
3.2.2 ケプラーの法則
3.2.3 日心座標・地心座標
3.2.4 地球の軌道
3.2.5 会合周期-火星の大接近
3.3 惑星達の集い
3.3.1 3惑星会合
3.3.2 4惑星会合
3.3.3 5惑星会合
3.3.4 グランドクロス
3.4 小惑星の話題
3.4.1 ついに2万個
3.4.2 登録と固有名
3.4.3 危ない小惑星
3.4.4 前代未聞
第4章 歴史の中の星物語
4.1 クリスマスはいつ?-ベツレヘムの星
4.2 陰陽師 安倍清明の見た星
4.3 惑星会合で見る中国古代史
付属CD-ROMの使い方
参考文献
索引
おわりに
内容説明
本書は、パソコンを使って楽しみながら天文学を学ぶことを目的として発行したものである。従来の教科書的な箇所も残っているが、できるだけ視覚的に理解できるように、多数の画像やシミュレーションソフトを付属CD‐ROMに収めた。これを使って深宇宙の彼方の銀河団の画像や美しい星座イラストが鑑賞できる。また、数千年前の星空や、将来起こるかもしれない小惑星とのニアミスなどが再現できる。火星の大接近や惑星直列の起こる日を捜し求めることもできる。しかも難解な数式は不要で、天文学やコンピュータの予備知識がなくても楽しめる。
目次
第1章 星座物語(おひつじ;おうし ほか)
第2章 星の世界への招待(天の座標系―歳差運動・星座名;星のエネルギー―物理諸量 ほか)
第3章 惑星運動(わが太陽系のメンバー;惑星軌道運動 ほか)
第4章 歴史の中の星物語(クリスマスはいつ?―ベツレヘムの星;陰陽師・安倍晴明の見た星 ほか)
著者等紹介
作花一志[サッカカズユキ]
1943年山口県に生まれる。1967年京都大学理学部宇宙物理学科卒業。1974年同大学理学研究科宇宙物理学専攻修了、理学博士。現在、京都コンピュータ学院鴨川校校長、京都大学総合人間学部非常勤講師。専門は計算天文学。銀河や星雲の発光メカニズムから惑星の軌道運動までを手がけ、特に惑星直列や小惑星とのニアミスなどを調査している。また、マルチメディア数学教材も制作している
中西久崇[ナカニシヒサタカ]
1969年奈良県に生まれる。1992年京都市立芸術大学美術学部美術科卒業。1993年京都コンピュータ学院情報処理技術科卒業。現在、京都コンピュータ学院非常勤講師、帝塚山高校非常勤講師。専門は版画(シルクスクリーン)・3D CG。最近は「コンピュータ・アルゴリズムのみによる『作品』の生成」をコンセプトとして作家活動を行っている
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。