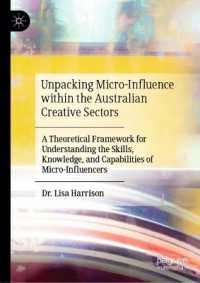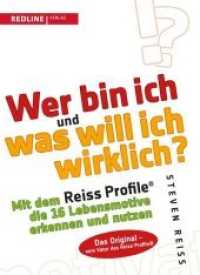内容説明
「折口信夫」―それは優れて近代の賜物だった。「折口学」の枠にとどまることなく、折口信夫(釈迢空)の作品・論考を近代文学研究の対象として捉えなおし、豊富な資料を基に本文評価・分析をおこないながら、その生成過程を探り、折口信夫思想の内実を改めて明らかにする。
目次
第1章 短歌の行方―様式・非短歌・生活・律・虚構(旅―短歌と学問とを架橋するもの;「叙事詩」と「語部」について―「折口語彙」の相対化;詩の形式と内容;釈迢空「非短歌」の意味;「非短歌」と東北探訪;「うみやまのあひだ」の変相;分節する歌集―『天地に宣る』論;未刊行本『歌虚言』―「虚構」の問題)
第2章 折口信夫 小説の意味―視覚と聴覚の交錯(「生き口を問ふ女」の構想;自伝的小説の系譜;「生き口を問う女」の続稿;「生き口を問ふ女」と「神の嫁」;「死者の書」のテクストとその生成)
第3章 『古代研究』への道(「語部論」の揺籃―折口信夫の発生;「わかしとおゆと」―折口信夫と金澤庄三郎;「古代研究」と国学の再興―折口信夫と柳田國男;昭和五年の折口信夫―東北・新野採訪の意味;柳田國男の「郷土」と折口信夫の「郷土」;「古代生活の研究」本文成立をめぐって)
終章 生成論研究の地平へ
著者等紹介
松本博明[マツモトヒロアキ]
1956年埼玉県川越市生まれ。國学院大學文学部卒業。同大学院博士課程後期単位取得満期退学。現在、岩手県立大学盛岡短期大学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 身体の知恵 〈下〉