- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 学術・教養
- > 学術・教養文庫その他
出版社内容情報
目次
<第1巻第1分冊>
第1部 資本の生産過程
第1篇 商品と貨幣
第1章 商品
第2章 交換過程
第3章 貨幣または商品流通
第2篇 貨幣の資本への転化
第4章 貨幣の資本への転化
第3篇 絶対的剰余価値の生産
第5章 労働過程と価値増殖過程
第6章 不変資本と可変資本
第7章 剰余価値率
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かわうそ
39
日本の現状を見るに、近代経済学は行き詰まりを見せている。金利を引き上げをすれば物価高は収まるだろうという経済学者の目論見は外れてしまっている。資本論は終わった。共産主義国の崩壊とともにそう高らかに宣言された。しかし、近代経済学こそがもしかしたら終わりを迎えているのかもしれない。そう思わせるほど、この本にはパワーがある。最も多くの人を突き動かしたと言っても過言ではない本書。労働者の立場ではおそらくは資本論の方が正しく見えてくるかと思う。読んでいるとうんうん。と頷きながら、思わず膝を打つ箇所が多い。2025/10/11
おたま
35
やっと読めた、という感じ。第1巻第1分冊。マルクス自身も「なにごとも初めが困難だ」と書いている通り、最初の第1分冊、特に最初の章である「商品」での議論が難しい。いわゆる「価値形態論」の部分。実は私たちの身の回りに普通にあり、あることが当たり前の「商品」について、その「価値」がどのように生成されてくるのか。「使用価値」「価値」それらの区分から始まり「貨幣形態」にまで至る部分。私たちが当たり前と思っているものを、再度理詰めで問い詰めていく、その構え自体を理解することが難しい。第1篇「商品と貨幣」を押さえれば⇒2022/04/02
Tomoyuki Kumaoka
20
「資本に転化するべき貨幣の価値変化はこの貨幣そのものには起こりえない」 「商品の再販売からも変化は生じない」 「貨幣所持者は市場で、(現実の消費そのものが労働の対象化であり、価値創造できる)独自な商品に出会うのである-労働力に」 労働が資本を生み出す過程を詳細に、論理的に記述。 翻訳本かつ古い本なので、脳に汗を書きながら読まざるを得ない。 ただ、対比、引用される本なので読んでおくと、ほかの本を読む際に理解度が高まるだろうか(こういう意味ではギリシャ哲学や聖書の内容について知っておきたい)。 2017/08/27
tharaud
9
これまでたくさんの入門書や解説書を読んできたが、いつかは原典、と思い挑戦。ようやく1冊読み終えた。マルクス自身も書いているが、最初の「商品」の章がやはり難しい。そのあとはおおまかには理解できる部分も意外と多い。佐々木隆治『資本論』、大谷禎之介『図解 社会経済学』をガイドとして読み進める。剰余価値のあたりになると、実感的に理解できる。次はいよいよ「労働日」だ。2024/08/12
Nobu A
7
途中から超早送り読了。何だろうこの読みづらさ。凡例、目次、第1版序文、第2版後記、フランス語版序文及び後記、第3版へ、英語版序文、第4版へと計68頁後にやっと第1章が 始まる。そして、文中に夥しい数とそれぞれが長い注釈。「商品は、まず第一に、外的対象であり、その所属性によって人間のなんらかの欲望を満足させる物である」と終始このような文章。漢字比率約半分。頭に残らない。読み込まれた方々には感服。気合いを入れ直して断食道場に携行でもしないと、熟読玩味は無理だな。完全な敗北感。続編2巻と3巻も手元にある。2021/06/14


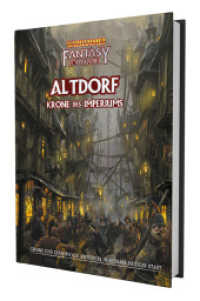

![月刊少年シリウス 2020年8月号 [2020年6月26日発売]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0872326.jpg)


