- ホーム
- > 和書
- > 教養
- > ノンフィクション
- > ノンフィクションその他
内容説明
田舎町の博物館で出会った黒人の剥製“エル・ネグロ”。人間が「標本」として展示されていることに衝撃を受けた青年は、パリ、バルセローナ、ケープタウンへと、その足跡をたどる旅に出る。人種、文化、アイデンティティをめぐる異色のルポルタージュ。
目次
1 人類展示室で―バニョレス 1983
2 ドレッドロック・ホリデイ―ジャマイカ 1985
3 メゾン・ヴェロー―パリ 1831
4 センデーロ・ルミノソ―ペルー 1987
5 グラン・カフェ・デ・ノベダデス―バルセローナ 1888
6 ふたつの顔を持つライオン―シエラレオネ 1995
7 エル・ネグロは残る!―バニョレス 2003
8 父祖の地で―南アフリカ 2004
著者等紹介
ヴェスターマン,フランク[ヴェスターマン,フランク][Westerman,Frank]
1964年、オランダ・エメンに生まれる。ワーヘニンゲン大学で熱帯農業を専攻。大学卒業後は、開発援助の仕事に就くかたわら、フリーのジャーナリストとして、カメルーン、キューバ、メキシコ、シエラレオネ、ルーマニア、旧ユーゴスラヴィアなどの諸国で活動する
下村由一[シモムラユウイチ]
1931年生まれ。千葉大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふみふむ
7
なかなか理解できなかったが、動物と同じように黒人が剥製にされて展示されていたことを追う中で、今でも膚の色での人種差別が根が深いこと。開発援助がどうしても先進国の傲慢になりがちなこと。貧困の背景等々を感じることができた。2011/03/09
やまざき
1
差別はダメゼッタイ、みたいな感じの表面的な話に終始していないのが良かった。著者の目線から見た世界が良く現されていて、ルポルタージュっていいな〜と思った。2022/11/12
AR読書記録
1
タイトルと出版社を見れば、およその内容はわかる気もする(“有色人種”が見せ物にされてた時代を知る、みたいな)、と思ったんだけど、いや今はもっと先の段階にいってたわごめん、という感想。“先進国”が“後進国”を搾取した歴史を反省し、“後進国”を助け教え導かねば、みたいな意識ももう過去のもので、反省はもちろんするけど、ではそこからどういう関係を築き直すべきだったのかを、フラットに考え直さねばならない、というところだと思う。この本の中で具体的な道筋が見えるとかではなく、ここから一人ひとりが意識をどう変えていくか。2021/03/16
100名山
0
非常に若々しい文章で始まります。 著者は19歳の時、友人とヒッチハイクでスペインの片田舎バニョレスにたまたま立ち寄ります。 彼を乗せてくれた地質学者が別れ際に「君たち文化に興味があるんだろう。それならバニョレスには立派な博物館があるよ。この州で一番古い博物館で、小人の黒人の剥製で有名なんだ。」と告げます。 そこで彼は入場料50ペタセを払い、黒人の剥製を観て、絵はがきを2枚買います。 狩猟の対象にさえしていた。 黒人を標本として一つの樽に爬虫類と一緒に塩漬でヨーロッパに送っていた事は分かりました。 2010/11/13
-
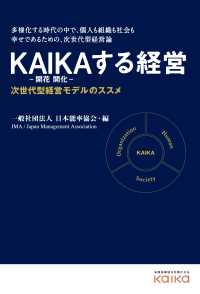
- 電子書籍
- KAIKAする経営 - 次世代型経営モ…








