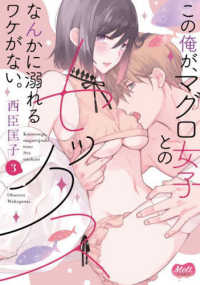内容説明
くりかえす苦難と矛盾の原点にある沖縄戦。その全容を、「集団自決」や住民動員のあり方など33の論点から多角的に検証。沖縄戦を「問い」として現在に引き継ぐための、第一人者による入門書。
目次
第1章 沖縄戦への道
第2章 米軍の上陸と沖縄戦の展開
第3章 沖縄戦のなかの人々
第4章 離島の沖縄戦
第5章 戦後の出発
第6章 なぜこれほどまでに犠牲が生まれたのか
著者等紹介
林博史[ハヤシヒロフミ]
1955年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。社会学博士。現在、関東学院大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Isamash
24
林博史・関東学院大学教授(1955年生まれ、一橋大社会学博士)2010年発行著作。昭和天皇が、沖縄戦で一撃を加えたいと和平提案を拒否したことが珍しく記されていた。本土防衛のための時間稼ぎの持久戦が方針であったのに関わらず、突撃をする羽目になったので、罪は深い。そして、沖縄戦で日本の軍隊が沖縄民間人に捕虜になることを一才許さず、無駄に多くの自死を強要した事実が説得力を持って語られている。婦女暴行も多発していて、米軍よりも寧ろ日本兵士の方が恐ろしいとの証言もあったとか。沖縄への差別意識が沖縄戦にモロに表出とか2024/05/26
二人娘の父
9
沖縄戦研究で多くの仕事をしてきた著者による2010年時点での総括的著作。一次資料として体験者の証言を基にしつつ、大本営と日本軍、また米軍側の資料も駆使しての分析である。本書の特徴は「検証」と題した33もの視点・論点を提起していること。今日的にも有効となるジェンダー視点などもあり、先見性を感じる。2010年といえば、集団自決についての議論が沸騰し、オスプレイ配備を含めて沖縄政界を大きく揺るがし、ついに「オール沖縄」という名の保革共同が生まれつつあった時期でもある。そうした背景を踏まえて読み込みたい。2023/07/12
大泉宗一郎
7
県民の4人に1人が亡くなったとされる沖縄戦。なぜこれほど多くの人々が亡くなったのかを、沖縄戦研究の第一人者である著者が膨大な一次資料からその構造を解き明かす。庶民らの証言を中心に検証がなされるが、戦争の残酷さや理不尽さに改めて胸を刺されるような想いになる。米軍の投降呼びかけでは戦陣訓を守る日本兵がいるガマではほぼ全滅、海外にいた島民が周囲を説得して自決を逃れるなどある程度パターンがあり、”異質”であることの重要性を説く。左派色が濃いが、徹底して庶民や弱者の目線から歴史を紡ごうとする著者の姿勢には共感する。2024/04/14
健康平和研究所
1
日本軍がいることで住民はアメリカ軍に保護されるよりは死を選ばされた 首里で日本軍が降伏しなかったことによって多くの民間人と兵士も殺された2019/09/06