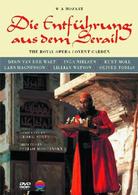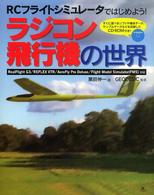出版社内容情報
古代、人間は野生の植物を食べていた。その後、人間の都合に合わせて品種改良して生まれた、身近な野菜たちの進化の歴史をたどる。
古代、人間は自然のなかに自生している野生の植物を食べていた。その後、「おいしい」「たくさんとれる」など、人間に都合のいいように品種改良して、現在の野菜が生まれた。原産地も含めて、身近な野菜たちのルーツをたどる。
◆既刊
?@米の物語
◆続巻
?B果物の物語(2015年10月)
?C食肉の物語(2015年12月)
【著者紹介】
ライター、エディター。主な作品『日本の農業』(構成・文、岩崎書店)、『身近な魚のものがたり』(著、くもん出版)、『農業に奇跡を起こした人たち(全4巻)』(著、汐文社)、『お米が実った!―津波被害から立ち上がった人びと』(著、汐文社)ほか。
目次
1 日本人が最初に作った作物はマメ類だった
2 古代になってたくさんの野菜が伝わった
3 城下町ができて野菜が売られるようになった
4 野菜のルーツとふしぎな世界
5 国が開かれいろいろ野菜が入ってきた
6 野菜の消費が増え各地に産地ができる
7 現在の野菜栽培を支える技術が生まれる
8 食生活が変化し野菜作りは新しい時代へ
9 野菜作りを支える技術開発が進む
著者等紹介
今田成雄[イマダシゲオ]
1954年、大阪府生まれ。東京大学大学院農学系研究科博士課程中退。1983年に農林水産省に入省し、農蚕園芸局、野菜試験場(現野菜茶業研究所)、東北農業研究センターに勤務。野菜の栽培生理研究に従事。現在、農研機構野菜茶業研究所野菜生産技術研究領域上席研究員。(農研機構:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)
小泉光久[コイズミミツヒサ]
1947年生まれ。国学院大学経済学部卒業。農業・農村、少子高齢化をテーマに執筆、製作に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
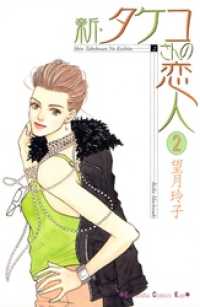
- 電子書籍
- 新・タケコさんの恋人(2)