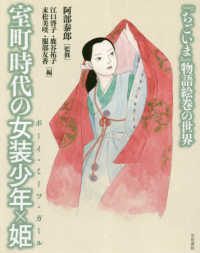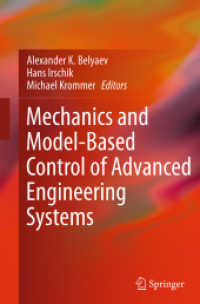出版社内容情報
男女平等をうたいながら、性差別的な言葉や行為に満ちた学校空間。差別と抑圧を超え、自己を解放する力をもたらすために教育に何ができるのか? 性差別の再生産を止め、既存の権力関係に変化をもたらそうとする新しいフェミニズム教育論!
[目次]
序章
第1章 フェミニズムとフェミニズム教育
1 権力をめぐるフェミニズムの考え方
2 構造としての権力関係への対応の仕方
3 女性学の誕生とその教育実践
4 フェミニズト・ペダゴジーによる権力関係への対応と失敗
5 権力関係の構造を変えるには
第2章 ポストフェミニズムにおける女性の主体性
1 頭のなかの得体のしれない力
2 ポストフェミニズム
3 ポストフェミニズムと新自由主義の共鳴
4 ポストフェミニズムの主体性
5 「作者とは何か」
第3章 学校教育のなかの二重基準と二重意識
1 学校がもたらす二重基準
2 二重基準への対応
3 W・E・B・デュボイスの論じた黒人の「二重意識」
4 学校現場の女性たちの二重意識
5 ハラスメントの構造――二重基準のあらわれ、そして二重意識を生み出すもの
6 バックラッシュと性差別――変化への抵抗
7 どちらの自己を養うのか
第4章 性差別はそこにあるのに、私たちはみんな見えなくさせられている
1 男子は落ちこぼれていない
2 リベラル・フェミニズムの教育研究
3 「男とか女とかことさら取り立てない」という学校文化
4 フェミニズムの意識を持つ教師
5 女子生徒たちの「抵抗」とポストフェミニズムとのつながり
第5章 困難な「セーフ・スペース」づくり
1 意識化
2 「習慣」の力
3 セーフ・スペース
4 権力が聞きたいことを繰り返す
5 女の語りは疑われる
第6章 情動のフェミニズム教育
1 身体を通じたコミュニケーション
2 エロスと情動
3 情動が伝わる教室環境
4 予測不可能なことを教室にもたらす情動
5 情動のコミュニケーションを習慣化する
終章
内容説明
教育にこそフェミニズムが必要だ!男女平等が前提とされる一方で、性差別的な言葉や行為に満ちた学校空間。とりわけ教師の無意識のふるまいが、女子たちに与える影響は大きい。差別と抑圧を超え、自己を解放する力をもたらすために、教育に何ができるのか?無意識の性差別の再生産を止めるために。従来のフェミニズム教育論が乗り越えようと奮闘してきた既存の権力関係に変化をもたらそうとする新しいフェミニズム教育論!
目次
序章
第1章 フェミニズムとフェミニズム教育
第2章 ポストフェミニズムにおける女性の主体性
第3章 学校教育のなかの二重基準と二重意識
第4章 性差別はそこにあるのに、私たちはみんな見えなくさせられている
第5章 困難な「セーフ・スペース」づくり
第6章 情動のフェミニズム教育
終章
著者等紹介
虎岩朋加[トライワトモカ]
1976年愛知県名古屋市生まれ。名古屋大学大学院教育発達科学研究科単位取得退学、ニューヨーク州立大学バッファロー校教育学研究科博士課程修了。Ph.D.in Social Foundations。名古屋大学国際協力推進本部特任講師、名古屋大学大学院教育発達科学研究科助教、敬和学園大学人文学部英語文化コミュニケーション学科准教授を経て、愛知東邦大学教育学部子ども発達学科准教授。教職課程担当。専門は、教育学、社会哲学。ジェンダー、フェミニズムを中心において教育理論研究を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。