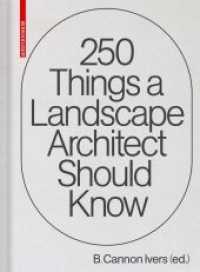目次
第1部 組織(地方自治と社会保障の権利;福祉行政と行政改革;社会福祉公的責任撤退の構図―地方分権で社会福祉事業はどうなるか;いわゆる「社会福祉事業団」の問題;名誉職委員制の源流と運命―ドイツ連邦共和国(西独)公的扶助における)
第2部 財政(憲法上より見た私的社会事業に対する公費支出の問題;「相扶共済」「負担の公平」―国保行政のイデオロギー的・法的問題;日本の社会保障と“三・七”闘争の論理;軍事大国化と社会保障制度の変貌;社会保障における勤労者負担の法構造;費用徴収制度検討の基本的視点)
著者等紹介
小川政亮[オガワマサアキ]
1920年東京に生まれる。1941年東京帝国大学法学部卒業。1942年軍隊(近衛歩兵、陸軍予備士官学校ほか)所属。1947年日本社会事業専門学校主事(のち教授)、日本社会事業協会社会事業研究所所員。1950年学制改革に伴い日本社会事業短期大学助教授。1958年学制改革に伴い日本社会事業大学助教授(のち教授)。1980年金沢大学法学部教授。1985年日本福祉大学社会福祉学部教授。1990年退職。1993年埼玉大学教育学部非常勤講師(2001年退職)。現在、日本社会事業大学名誉教授、全国老人福祉問題研究会名誉会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。