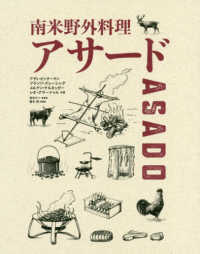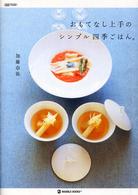出版社内容情報
鍼灸診療の基礎から最新の気の医学まで幅広く紹介!
初学者にもわかりやすい内容に全面リニューアル!
内容紹介
●2006年発行の『新しい鍼灸診療』を,新たな編者陣で全面刷新.第2版では,新たに「伝統鍼灸を活用した新しい鍼灸診療」として,「北辰会方式」「VAMFIT(経絡系統治療システム)」「経筋治療」を追加した.
●伝統鍼灸から現代鍼灸までを網羅した上で,「気の医学」としての鍼灸治療を多角的に学ぶことができるテキスト.
目次
カラー舌所見の種類
第1章 鍼灸医学の創造的再構築
1.東洋医学原論の構築に向けて
1)澤瀉久敬と東洋医学原論
2)広義の医学・医療行為
(1)医学
(2)医療行為
(3)伝統医学
2.東洋医学の起源と特徴
1)日本における医学・医療の歴史
(1)初期(受容期)
(2)後世派期
(3)古方派期
(4)洋方派期
(5)東洋医学復興期
2)東洋医学の特徴
3.鍼灸医学の学・術・道
1)学(哲学・科学・全一学)
2)術(技術・仁術・技能)
3)道(自然観・生命観・健康観・病気観)
(1)自然観(生物的自然・物質的自然・根源的自然)
(2)自然治癒力
(3)生命観
(4)健康観・病気観
4.気を認知する(印知:生命感覚,感知:共通感覚)
1)東洋医学の源流(気の医学・場所の医学)
2)伝統的鍼灸医学(液体医学)
3)近代的鍼灸療法(固体医学)
4)印知感覚における気の認知
5.日本の鍼灸医学の現状と課題
第2章 現代の鍼灸医療
I 伝統的鍼灸医学における診察法の実際
1.望 診
1)全体望診
(1)神
(2)色
(3)形
(4)態
2)顔面診
3)局所望診
(1)眼
(2)鼻
(3)口
(4)髪
(5)耳
(6)歯齦
4)舌診
(1)舌診の方法
(2)正常の舌所見
(3)舌質
(4)舌苔
(5)舌所見からみた予後判断
(6)舌所見の捨従
(7)舌所見と症候が一致しない場合
5)爪甲診
(1)爪の色
(2)爪の形
(3)爪の半月
2.聞 診
1)声診の意義
(1)声の高さ
(2)声の大きさ
(3)声質
(4)話し方
2)五音
3)五声
4)発語の異常
5)呼吸の異常
6)異常音
7)気味
3.問 診
1)医療面接と問診
2)問診の流れ
(1)初診時の問診例
(2)再診時の問診例
3)東洋医学の診断に必要な問診項目
(1)十問歌
(2)寒熱
(3)汗
(4)痛み
(5)二便(大便・小便)
(6)飲食
(7)胸腹部の問診項目
(8)耳部の問診項目
(9)目部の問診項目
(10)鼻部の問診項目
(11)睡眠
(12)婦人
(13)小児
4.切 診
1)脈診
(1)脈診する部位
(2)寸口診法
(3)脈状診
(4)祖脈(基本の脈状)
(5)脈状の複合
(6)七表八裏九道
(7)脈の順逆
(8)脈の捨従
(9)脈状の変化による予後判断
(10)怪脈(死脈)
(11)脈差診
(12)六部定位脈診
2)体表診察
3)腹診
(1)平人無病の腹
(2)腹診の方法
(3)腹診の種類
(4)難経系腹診
(5)意斉・夢分流の腹診
(6)漢方腹診
(7)募穴診
(8)臍診
4)背診
(1)背診における部位名
(2)背診の方法
(3)背部兪穴
(4)背診における五臓反応
(5)胸椎棘突起の反応と病症
(6)背部反応と病症
5)切経
(1)切経の方法
(2)撮診
6)切穴
(1)切穴の方法
(2)基本的なゆ穴反応の様式
(3)原穴診
5.経絡・経穴・反応点
1)経絡
2)十二経脈の流注
3)奇経八脈の流注
4)ゆ穴
5)経穴の名前の由来
6)経絡と経穴の関係
7)交会穴
8)要穴
9)経絡・経穴の国際標準
10)取穴の尺度
11)経穴の取穴に必要な用語
(1)方向に関する用語
(2)経穴部位を理解するための体表指標
12)経穴部位の標準化
13)選穴方式のバリエーション(経穴の選び方)
(1)局所的・局部的選穴
(2)内臓体壁反射を介した選穴
(3)経脈流注に基づく選穴
(4)証または穴性を考慮した選穴
(5)肩こりのバリエーション
14)経絡・経穴に関する新しい知見―発現する経絡・強力反応点
II わが国における鍼灸治療の実際
1.経絡治療
1)経絡治療の成立
2)脈診による診断
3)脈診のランク
(1)脈差診
(2)祖脈診
(3)脈状診
(4)脈位脈状診
(5)経絡治療の証
4)経絡治療を取り巻く諸問題
2.近代的鍼灸治療
1)物理療法的鍼灸療法
(1)現代医学的な病態把握に基づいた鍼灸治療
(2)物理療法の概要
(3)物理療法としての鍼灸治療の実際
(4)腰部脊柱管狭窄症を例にあげて
(5)腰部脊柱管狭窄症に対する鍼灸治療のまとめ
2)トリガーポイント療法
(1)トリガーポイントの意義
(2)トリガーポイントの探し方
(3)トリガーポイント療法の実際
(4)トリガーポイント鍼療法
3.中医学における鍼灸治療
1)鍼灸の治療作用
(1)疏通経絡
(2)扶正きょ邪
(3)調和陰陽
2)鍼灸治療の原則
(1)治神と得気
(2)清熱と温寒
(3)補虚と瀉実
(4)標治と本治
(5)弁病と弁証
3)鍼灸弁証論治の要点
4)鍼灸の配穴処方
(1)選穴原則
(2)配穴方法
(3)鍼灸処方の構成
4.臓腑経絡学説に基づく新しい鍼灸診断・治療法
1)現状の診断・治療システムの特徴と課題
2)診療方式の特徴と基本的フレーム
3)診療方式の種類
4)臓腑病証,経脈病証,経筋病証,外感病証
5)証の重層構造
6)臓腑病証の診断
7)経脈病証の診断
8)経筋病証の診断
第3章 伝統鍼灸を活用した新しい鍼灸診療
I 北辰会方式
1.治療方式の概要
1)現代中医学理論をベースとする
(1)医学としての論理性
(2)医学史・各家学説
(3)共通言語
2)体表観察を駆使
(1)特徴的な診断意義を踏まえる
(2)左右差を重視
(3)フェザータッチの活用
3)胃の気の脈診
4)病因病理を重視
5)空間論を診断・治療において活用
6)選穴について
7)少数鍼(原則1穴)
(1)効果判定からよりよい選穴を模索しやすい
(2)片側1穴に刺鍼する
(3)置鍼を基本とする
8)正邪弁証
(1)正気虚程度と負荷試験
(2)難病治療
9)撓入鍼法
10)刺入しない鍼―打鍼・古代鍼
(1)打鍼
(2)古代鍼
11)太極陰陽論
2.診察方法
3.治療方法
4.症例
II VAMFIT(経絡系統治療システム)
1.VAMFITの概要
1)「VAMFIT(経絡系統治療システム)」について
2)基本証と異常経絡(寒熱波及経絡)について
3)VAMFITによる治療の流れ
2.VAMFITによる診察部位と考え方
1)愁訴が上肢や下肢にある場合の診断
(1)愁訴が上肢や下肢にある場合の診断部位について
2)愁訴が体幹部や頭部にある場合
(1)愁訴が体幹部や頭部にある場合の診断部位について
(2)“経絡系統”すべての診断を頸部で行う
(3)「頸入穴」を診断点,「下合穴」と「絡穴」を確認穴とする
3.VAMFITによる異常経絡(寒熱波及経絡)のみつけ方
1)愁訴部位の位置で異常経絡(寒熱波及経絡)をみつける
2)頸部運動による愁訴の出現部位によりみつける
3)頸入穴触診によりみつける
4.VAMFITによる異常経絡(寒熱波及経絡)への治療方法
1)異常経絡(寒熱波及経絡)を確認する
2)要穴への刺鍼
3)複数経絡異常の場合
5.霊背兪穴VAMFITについて
1)霊背兪穴VAMFITの例(霊背兪穴を使った体前屈兪穴テスト)
6.すべての「経絡系統」の異常に対応する
7.経脈治療・経別治療について
1)絡脈治療
2)経別治療
8.経筋治療について
9.奇経治療について
1)八総穴による奇経治療の例
2)「新治療システム」による奇経治療の例
10.症例
III 経筋治療
1.経筋病モデルとしての遅発性筋痛
2.新しい経筋治療
3.経筋病の診断と治療
1)動作時の痛みがあれば経筋病
2)愁訴と関連する経筋ルートの異常
3)経筋病の治療はえい穴,兪穴の圧痛点
4)治療(刺激)方法
4.経筋治療の症例
第4章 気の医学―気・経絡
はじめに
I 鍼灸医学の立場から
1.機能調節系としての経絡システム
1)ホログラム理論による身体観
2)顔面と臓腑との関係
3)腹部と臓腑との関係
4)経絡系統
5)皮膚と経絡
6)奇経八脈
7)現代医学と東洋医学の視点の違い
8)運動器系愁訴に特化した「経筋」
9)経筋治療の有効性
10)局所だけでなく経筋上に広く出現する反応
11)反応があればどの経穴も有効か
2.鍼灸臨床と気
1)鍼灸医学の立場からみた気
2)邪気
3)気を認識することは可能か
4)経脈と経絡
5)経絡は存在するか
6)経穴の意味
7)灸をしてはいけない場合
II 気診の立場から
1.気診までの道のり
1)小田一のあゆみ
2)経絡の電気磁気的考察
3)イオンパンピングとダイオード
2.Oda testの基本的事項
1)胸鎖乳突筋を調べる方法
2)Oda testの練習方法
3)筋緊張の条件づけ
4)音素コード
3.磁石診断とダイオード診断
1)胸鎖乳突筋の緊張
2)両者対等二者択一の診断
3)ダイオード・リングによる診断
4)脈診に代わる経気診断法
III 湯液・鍼灸作用同一論の立場から
1.印知の臨床作用
2.印知の解釈―自然科学的方法論
3.印気・気滞
4.経絡・経穴・有川反応点
5.湯液・鍼灸作用同一論と臨床応用
1)経過―処置,五感による所見および印知で捉えた所見
2)五感による事実と印知による所見および解釈
3)有川のコメント
4)印気による医療を新しい学問として捉えることの意義
第5章 新しい鍼灸診療
はじめに
I Bi-Digital O-Ring Test(BDORT)による診療システム
1.Bi-Digital O-Ring Testと経絡現象
1)BDORTによる経絡学研究の可能性
(1)BDORTを用いた経脈・経穴の描画
(2)BDORTの臨床的応用
(3)BDORTの仕組み
2)経絡現象
(1)鍼の響き・鍼響と経絡現象
(2)鍼響の速さと持続時間
(3)肺経における経絡現象の結果比較
3)BDORTからみた経絡現象
(1)黒川・北出のBDORT研究結果
(2)経絡現象・研究の要約
2.気の重要性とBi-Digital O-Ring Test
1)気の究明は情報科学
2)BDORTで何がわかるのか
3)BDORTにて生体情報を知る
(1)BDORTにおける情報的相互作用
(2)BDORTによるイメージング法と薬剤の適合・適量
(3)歯科治療における鍼灸医学とBDORT
(4)免疫,ストレス度のチェックおよび心理状態を把握
(5)BDORTによる気の虚実証
4)歯科治療を効果的にする気の導入
5)気の導入効果の客観的臨床的観察
II 鍼灸気診による診療システム
1.身体に出現する治標法・治本法・局所法の孔穴
1)治標法・局所法
2)治標法・局所法における標識経気
3)治本法と3つの治法経気
4)円柱状経気の中の情報
5)手指関節の反応の優位診断
6)鍼灸診断と漢方診断
(1)鍼灸診断のための標識経気の診断
(2)漢方診断のための標識経気の診断
III 生体気診による診療システム
1.生体気診による統合医療
1)気を診断する
2)気の井上式把握技法
(1)井上式気診法の姿勢
(2)テスターとセンサー
(3)気診の実施要領
(4)判定方法
(5)陰:陽の診断
(6)望視法
3)気診における注意すべき事項
4)気診の練習法
5)練習上の注意
2.気による診断の応用法
1)薬物の適応診断
2)鍼灸の気診による診断法
3.症 例
IV 入江フィンガーテストによる診療システム
1.入江フィンガーテストの実際
1)テスター―FTは相対性理論
2)センサー―目的に応じた使い分け
2.鍼灸と湯液が統合された入江FTシステム
1)FTシステムは臓腑経絡学説
2)最初にマスターすべき経別脈診
3)FTシステムを用いた診断と治療―誤治しないために
4)FTシステムのメリット
3.経 筋
1)経筋診断の実際
2)経筋治療の実際
3)経筋症治療の実例
4.奇 経
1)奇経の診断法
2)奇経の治療法
(1)シングル治療
(2)ペア治療
3)奇経治療の実例
5.虚実と補瀉
6.イメージ診断
1)病名診断への応用は慎重に
2)イメージ診断が許される疾患
3)経穴部位診断に最適
7.FT診療25年を経て―それでも西洋医学がないと
1)経絡医学の限界を解決したデルマトームの図
2)鍼灸の適応決定に西洋医学は不可欠―高齢女性の腰痛とMRI検査
3)おわりに
(1)経別脈診と経別IP療法は必要か?
(2)気診(FT)をはじめる前に
(3)経筋治療はえい穴の円皮鍼がよい
V 原始信号系による診療システム
1.気滞を消去すれば疾病は治癒の方向に向かう
2.印知能力が芽生えるまで
3.人間のもつ五感以外の感覚
4.経絡の図説―現れる経絡
5.有川反応点を刺激して有効であった腹痛,腰痛,頭痛の症例
さくいん
著者所属/略歴 ※本書が刊行された当時のものです.現在とは異なる場合があります.
【編者略歴】
篠原昭二【しのはらしょうじ】(鍼灸学博士)
1978年 龍谷大学法学部卒業
〃 明治東洋医学院専門学校卒業
1980年 明治鍼灸短期大学助手
1987年 明治鍼灸大学講師
1991年 明治鍼灸大学助教授
2003年 明治鍼灸大学,同・大学院教授
2008年 明治国際医療大学,同・大学院教授
2014年 九州看護福祉大学教授
2015年 九州看護福祉大学教授,同・大学院教授
和辻 直【わつじただし】(鍼灸学博士)
1987年明治鍼灸大学鍼灸学部卒業
1989年明治鍼灸大学附属研修鍼灸師修了
1991年明治鍼灸教員養成施設卒業 明治鍼灸大学助手
1994年明治鍼灸大学講師
2004年明治鍼灸大学助教授
2005年明治鍼灸大学大学院助教授
2008年明治国際医療大学,同・大学院助教授
2015年明治国際医療大学教授
北出利勝【きたでとしかつ】(医学博士)
1965年 立命館大学経営学部卒業
1968年 京都仏眼鍼灸理療専門学校卒業・鍼灸師免許取得
1968~1980年 大阪医科大学附属病院麻酔科(兵頭正義教授に師事,鍼灸臨床)
1980年 明治鍼灸短期大学(3年制)助教授
1988~2010年 大阪医科大学麻酔科学教室非常勤講師
1990年 明治鍼灸大学(現・明治国際医療大学)教授
2011年 明治国際医療大学名誉教授
目次
第1章 鍼灸医学の創造的再構築(東洋医学原論の構築に向けて;東洋医学の起源と特徴 ほか)
第2章 現代の鍼灸医療(伝統的鍼灸医学における診察法の実際;わが国における鍼灸治療の実際)
第3章 伝統鍼灸を活用した新しい鍼灸診療(北辰会方式;VAMFIT(経絡系統治療システム) ほか)
第4章 気の医学―気・経絡(鍼灸医学の立場から;気診の立場から ほか)
第5章 新しい鍼灸診療(Bi‐Digital O‐Ring Test(BDORT)による診療システム
鍼灸気診による診療システム ほか)
著者等紹介
篠原昭二[シノハラショウジ]
鍼灸学博士。1978年龍谷大学法学部卒業。明治東洋医学院専門学校卒業。1980年明治鍼灸短期大学助手。1987年明治鍼灸大学講師。1991年明治鍼灸大学助教授。2003年明治鍼灸大学、同・大学院教授。2008年明治国際医療大学、同・大学院教授。2014年九州看護福祉大学教授。2015年九州看護福祉大学教授、同・大学院教授
和辻直[ワツジタダシ]
鍼灸学博士。1987年明治鍼灸大学鍼灸学部卒業。1989年明治鍼灸大学附属研修鍼灸師修了。1991年明治鍼灸教員養成施設卒業。明治鍼灸大学助手。1994年明治鍼灸大学講師。2004年明治鍼灸大学助教授。2005年明治鍼灸大学大学院助教授。2008年明治国際医療大学、同・大学院助教授。2015年明治国際医療大学教授
北出利勝[キタデトシカツ]
医学博士。1965年立命館大学経営学部卒業。1968年京都仏眼鍼灸理療専門学校卒業・鍼灸師免許取得。1968~1980年大阪医科大学附属病院麻酔科(兵頭正義教授に師事、鍼灸臨床)。1980年明治鍼灸短期大学(3年制)助教授。1988~2010年大阪医科大学麻酔科学教室非常勤講師。1990年明治鍼灸大学(現・明治国際医療大学)教授。2011年明治国際医療大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。