出版社内容情報
「和食」がおもしろい! 今に伝わる調味料・料理法のルーツを探る!
江戸懐石料理を伝える近茶流嗣家・柳原尚之さんが江戸時代の資料(今でいうレシピ本)に出てくる料理を再現。さらに現代風にアレンジした料理を紹介します。その昔、人々は創意工夫を重ねて江戸料理の基礎をつくりあげました。江戸料理は、今に伝わる料理のルーツを探ることができ、その料理法には興味深いものがたくさんあります。醤油が普及する前、調味料として使われていた「煎り酒」、最近ブームになった麹は「塩麹」ではなく「練り麹」として使われていた、うなぎの蒲焼きの「蒲」とは?など、知っておきたい内容がもりだくさんです。
春~奈良茶飯、寄せ菜、桜煎、巻繊(けんちん)
初夏~ぬた、たで酢、きらず、小川たたき
夏~阿茶蘭漬け、かば焼き、水造り、水仙
初秋~幽庵焼き、こけらずし、和蘭陀煮、練り?、あつもの
秋~利久、しぎ焼き、みなと
冬~もうりやう、せんば、風呂吹き、太煮、煮貫
早春~淡雪、霜降る、酢入り、田夫
【著者紹介】
近茶流 嗣家、柳原料理教室副主宰。父・近茶流宗家、柳原一成とともに東京赤坂の柳原料理教室にて、日本料理、茶懐石の研究指導にあたる。日本料理を海外に広める活動も行い、海外でのイベントや料理講習会にも多く参加するほか、ドラマや時代劇の料理指導、料理所作指導、料理時代考証も数々手がける。
内容説明
料理、食材、時代背景を探り、食を楽しむ。江戸時代からの知恵と技を現代へ受け継ぐ。「おいしい」の本質がわかる。
目次
第1章 春(煎り酒;寄せ菜 ほか)
第2章 初夏(小川たたき;たで ほか)
第3章 夏(阿茶蘭漬け;水仙 ほか)
第4章 初秋(こけらずし;和蘭陀煮 ほか)
第5章 秋(利休;しぎ焼き ほか)
第6章 冬(煮貫;せんば ほか)
第7章 早春(酢煎り;田夫 ほか)
著者等紹介
柳原尚之[ヤナギハラナオユキ]
近茶流嗣家。柳原料理教室副主宰。東京農業大学農学部醸造学科にて発酵食品学を学ぶ。卒業後、小豆島のしょうゆ会社の研究員として勤務。その後、オランダ船籍の帆船のキッチンクルーを経て、現在は、父・近茶流宗家、柳原一成とともに東京赤坂の柳原料理教室にて日本料理、茶懐石の研究指導にあたる。日本料理を海外に広める活動も行い、海外でのイベントや料理講習会での指導経験も多数。2008年から5年間、東大寺のお水取りに参籠し、練行衆の菜を作る「院士」を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- 【分冊版】悪役令嬢後宮物語 33話(ア…
-

- 電子書籍
- 愛は復讐の果てに〈パーフェクト・ファミ…
-

- 電子書籍
- 根津さんの恩返し 第17話 コミックブ…
-
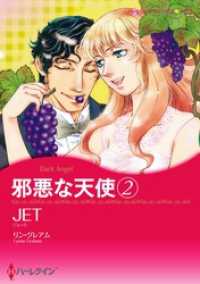
- 電子書籍
- 邪悪な天使 2【分冊】 2巻 ハーレク…
-

- 電子書籍
- 東方三月精 Visionary Fai…




