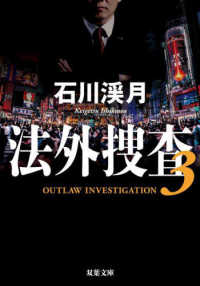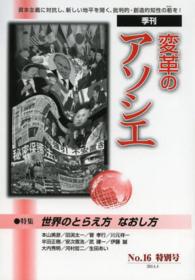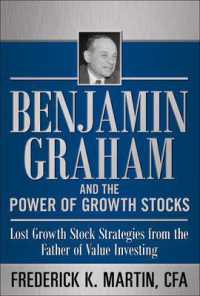出版社内容情報
《内容》 医療倫理はケースで学ぶ! 医療現場で直面する倫理的な葛藤,判断に悩む27ケースについて2通りのアプローチでどのように問題整理し,よりよい判断へとつなげていくのか,医学・看護学・哲学・倫理学・法学等の専門家が多角的な視点から論じた。日々新たに生じる倫理的課題は豊富なトピックスとコラムで紹介。
《目次》
はじめに--本書を使われる皆さんへ
Approach 1
■成人期の課題
Case 1 医療者の指示に従わない患者
Case 2 がんの告知
■終末期の課題
Case 3 安楽死・尊厳死
Case 4 セデーション(鎮静)
■脳死と臓器移植
Case 5 脳死
■老年期の課題
Case 6 在宅患者への医療・介護
Case 7 痴呆高齢者のリハビリテーション
■青年・成人期の課題
Case 8 HIV/AIDS
Case 9 人工妊娠中絶
■小児期の課題
Case10 子どもへの病気説明
Case11 子ども虐待
■出生時の課題
Case12 体外受精
Case13 出生前診断
■現場の人間関係
Case14 同僚のミス
Case15 対応の難しい患者
■研究倫理
Case16 研究の倫理
Approach 2
Case 1 医師,看護師,家族それぞれの思い
Case 2 患者への内服治療の説明
Case 3 痴呆高齢者の転倒・転落事故
Case 4 職場における感染症への対応
Case 5 信仰上の理由による治療拒否
Case 6 重度の障害をもつ新生児の治療
Case 7 義父の精子を使用したAID
Case 8 悪い病名や予後をどのように伝えるか(1)
Case 9 悪い病名や予後をどのように伝えるか(2)
Case10 悪い病名や予後をどのように伝えるか(3)
Case11 誰が研究論文の著者になるのか
あとがき
内容説明
医療現場で直面する倫理的ジレンマ、判断に悩む27ケースについてどのように問題点を整理し、よりよい対応へとつなげていくか、2つのアプローチを通して、具体的に解説。
目次
1 (成人期の課題;終末期の課題;脳死と臓器移植;老年期の課題;青年・成人期の課題 ほか)
2 (医師、看護師、家族それぞれの思い―思いがわからないなかでのジレンマ;患者への内服治療の説明―情報提供に差があってもよいのか?;痴呆高齢者の転倒・転落事故―物理的・人的資源に限界があるなかでの対応;職場における感染症への対応―インフォームド・コンセントと守秘義務;信仰上の理由による治療拒否―患者の希望に医療者はどこまで従わなければならないのか ほか)
著者等紹介
赤林朗[アカバヤシアキラ]
1983年東京大学医学部卒業。内科研修後、ヘイスティングスセンター客員研究員、東京大学大学院医学系研究科・健康科学・看護学専攻講師を経て、現在は京都大学大学院医学研究科教授
大林雅之[オオバヤシマサユキ]
1977年横浜市立大学文理学部卒業。上智大学大学院修了後、ジョージタウン大学客員研究員、山口大学医学部教授を経て、現在は川崎医療福祉大学医療福祉学部教授。専攻は生命倫理学、科学史、科学哲学
家永登[イエナガノボル]
1974年東京都立大学法学部卒業。北里大学医学部講師を経て、2002年から専修大学法学部助教授
白浜雅司[シラハママサシ]
1983年九州大学医学部卒業後、佐賀医科大学総合診療部入局。1994年より三瀬村国民健康保険診療所所長。1999年より佐賀医科大学臨床教授を兼任
中尾久子[ナカオヒサコ]
1977年九州大学医療技術短期大学部看護学科卒業、1997年山口大学大学院経済学研究科修了。大学病院に勤務後、産業医科大学医療技術短期大学講師を経て、1996年より山口県立大学看護学部助教授。専攻は成人・老人看護学、山口大学大学院医学研究科在籍中
村岡潔[ムラオカキヨシ]
1993年大阪大学医学部大学院単位取得。同大学環境医学シニア医員を経て、1998年より仏教大学文学部助教授。医療文化研究センターにも所属
森下直貴[モリシタナオキ]
1983年東京大学大学院人文学研究科博士課程単位取得退学。1987年浜松医科大学医学部倫理学助教授、2002年教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たろーたん
jiro