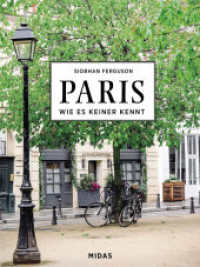出版社内容情報
何かしゃべろうとすると最初の言葉を繰り返してしまう(=「連発」という名のバグ)。それを避けようとすると言葉自体が出なくなる(=「難発」という名のフリーズ)。吃音とは、言葉が肉体に拒否されている状態です。しかし、なぜ歌っているときにはどもらないのか?なぜ独り言だとどもらないのか?従来の医学的・心理的アプローチとはまったく違う視点から、徹底した観察とインタビューで吃音という「謎」に迫った画期的身体論!
伊藤 亜紗[イトウ アサ]
著・文・その他
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
s-kozy
93
非常に興味深い本。面白いです。吃音を当事者へのインタビューも交えて分析した本書。序章にあるように吃音は「体のコントロールを外れたところに生起する経験」。人はこれに対処しようとするし、結果、これが二次的な症状に繋がりもし、コントロールし直そうとすることでそれにとらわれもする。「自分の体を動かしているのは誰か?」要するに「自分とは何か」に直結する話題。吃音を切り口としながら、それにとどまらない現代人の身体論にしっかりと迫ってくる一冊。読書の面白さを感じさせてくれる。お勧め。2018/11/13
どんぐり
86
<シリーズケアをひらく>の一冊。このシリーズはユニークで、瞠目すべき良書が多い。著者の目の見えない人の本も面白かったけれど、こちらも面白い。どもる人が自分の不自由さにどう向き合い対処しているか、「連発」「難発」「言い換え」「ノる」「乗っ取られる」といった“どもる体”の現象に迫る。「たたたたたたまご」の連発に、特定のことばを発するのにフリーズする難発、そのために違うことばで言い換え、どもらなければ使えるはずのことばの辞書ができあがる。リズムに乗せて発すると、なぜかことばがスムーズにでてくる不思議。なかでも、2020/08/07
アキ
84
しゃべるとは自動化された身体運動であり、どもるとはもうひとりの自分と調整しながら生きるということ。私を超えていく体という存在の面白さと誠実であることなのだ。マリリン・モンローもルイス・キャロルも吃音だったんですね。「目に見えない人は世界をどう見ているのか」に引き続き著者の本は刺激的で読みやすい。実際の吃音の方たちへのインタビューをおこし、丁寧に分析していて好感が持てる。聞く側としても、どもる方がいらっしゃるとしても全面的に受け入れます。ベートーベンの「運命」を聞くときのように、ダダダダーン!これは違うか?2021/01/31
こばまり
71
坦懐で前向きな好奇心に満ちていて、読者を高揚させるこの感じがあの本の読後感とよく似ていると思えば、果たして著者はあの本こと、『目の見えない人は〜』の伊藤氏であった。考察の広さと深さにワクワク。医学書院の「ケアをひらく」シリーズは名著揃いだ。2021/04/04
ネギっ子gen
63
『目の見えない人は世界をどう見ているのか』で、視覚がない人から見える世界を切り取るなど、様々な「人体の不思議」を研究している著者が、当事者以外にはミステリアスな吃音障害を、言語的活動ではなく身体的経験として捉え直す試み。どもる状態の時、身体に何が起きているのかを、著者独自の研究と当事者へのインタビューを通じて解明。「吃音」という人体の謎のひとつを分析した身体的吃音論。著者紹介頁で、<趣味はテープ起こし。インタビュー時には気づかなかった声の肌理や感情の動きが伝わってきてゾクゾクします>と。この記述に共感。⇒2021/02/16