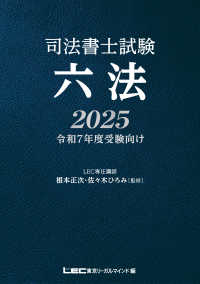出版社内容情報
ゴミは見つけるけれど拾えない、雑談はするけれど何を言っているかわからない――そんな不思議な「引き算のロボット」を作り続けるロボット学者がいる。彼の眼には、挨拶をしたり、おしゃべりをしたり、歩いたりの「なにげない行為」に潜む“奇跡”が見える。他力本願なロボットを通して、日常生活動作を規定している「賭けと受け」の関係を明るみに出し、ケアをすることの意味を深いところで肯定してくれる異色作!
内容説明
ひとりでできないもん―。他力本願なロボットがひらく、弱いという希望、できないという可能性。「賭けと受け」という視点から、ケアする人される人を深いところで支える異色作。
著者等紹介
岡田美智男[オカダミチオ]
1960年生まれ。電子工学を本格的に学ぼうと大学に進学するも、偶然の出会いも手伝って、音声科学、音声言語処理、認知科学、生態心理学、社会的相互行為論、社会的ロボティクスなどの分野を行きつ戻りつ、現在に至る。東北大学大学院工学研究科博士課程修了後、NTT基礎研究所情報科学研究部、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)などを経て、豊橋技術科学大学情報・知能工学系教授。専門は、コミュニケーションの認知科学、社会的・関係論的ロボティクス、ヒューマン‐ロボットインタラクション、次世代ヒューマンインタフェースなど(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スノーマン
27
専門的な部分はだいぶ読み飛ばしてしまったものの、それでも面白い!ロボットのイメージを一新する、頼りなさ。その頼りなさ、弱々しさ。人間だって色んな人がいる。こういうロボットが認められる世界。素晴らしい。2018/12/21
K1
15
「弱さ」はネガティブなイメージを伴う言葉だけれど、それを受け入れたうえで、それを積極的に生かせないかーあきらめではないけれど、うまくつきあっていけたら、「弱さ」を越える、むしろ「弱さ」をちからに変えていくような、ポジティブな側面も拓けてくるのではないかー強いばかりの人などいないのだから。2020/12/16
うぉ
15
道に落ちているゴミのそばに佇み、通りすがりの誰かがゴミを拾って入れてくれるのを待っているゴミ箱ロボット。自律的に歩けるロボットではなく、人に働きかけて移動させてもらうようなロボット。そんなユニークなロボットを社会に提案する方が書いた本。モノではなく関係性のかたちとしてロボットを捉えるのは新鮮で、人間的な温かみがあるロボットの在り方を示唆しているようだった。2019/07/14
スイ
13
著者が研究しているのは、何と一人では役に立たないロボット。 人間が手を貸すことで役目を果たせる、その考えはとても新鮮で驚いた。 雑談とロボット、そこから人間を省みる。 何でも一人で出来なくていいのだ、とどこか張り詰めていたものが緩む。 「自立というのは何にも依存しないことではない、依存先がたくさんあるからそれぞれへの依存の度合いが少なく、一見一人で立っているように見えることだ」という話が好きなのだけど、それに通じるものもあり、とても興味深い読書だった。2017/04/12
貧家ピー
10
自分でゴミを拾えないゴミ箱ロボット、答えを間違えるロボットなど、人の助けを借りないといけない「弱い」ロボットを開発するに至った経緯、周囲の反応などをまとめた。人の役に立つのがロボットという思い込みから、弱いロボットというのは新鮮だった。不完全なところを隠さう、その弱さを開示することで、周りにいる人の強みや優しさをうまく引き出すことが出来るのが面白い。2023/11/25
-

- 電子書籍
- 転生したら王女様になりました262話【…
-
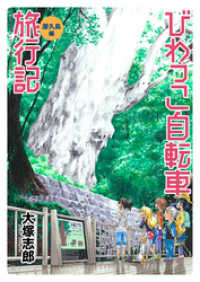
- 電子書籍
- びわっこ自転車旅行記 屋久島編 ストー…