出版社内容情報
《内容》 臨床現場で最も具体的なかたちで受け入れられ、評価の高い『オレム看護論』第6版の翻訳。「サービス・社会的・対人的としての看護」、「看護知識の体系化」、「システムとしての看護を構成する要件」、「実践としての看護」の4部構成に変わった。オレム理論の良き理解者であるSusan Taylor博士らが共著者として参加した『オレム看護論』の決定版。
《目次》
プロローグ
第1章 ヒューマンサービスである看護を理解するための序
第1部 看護のサービス,社会的・対人的特徴
第2章 看護の理解
第3章 個々人の人間的条件と看護要件
第4章 看護と社会
第5章 看護の対人関係的特徴
第2部 看護知識の形式化
第6章 看護についての見解,人間についての見解
第7章 セルフケア不足看護理論
第8章 看護実践科学
第9章 健康とヘルスケア
第3部 看護システムの変数
第10章 治療的セルフケア・デマンド:患者変数
第11章 セルフケア・エージェンシーと依存的ケア・エージェンシー
第12章 看護エージェンシー:看護師変数
第4部 看護の実践
第13章 看護の実践:サービス単位としての個人
第14章 多人数状況,家族,コミュニティにおける看護の実践
第15章 看護師
付録A 看護歴の要素
付録B セルフケア不足看護理論開発の歴史
付録C 普遍的セルフケア要件の充足に影響を及ぼす障害物とその他の要因
用語解
文献
訳者あとがき
索引
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
つなぐ
1
オレム看護論は、セルフケアの不足に対する専門的援助として看護サービスを定義している点において、環境調整に力点をおくナイチンーゲールの何十倍も看護の定義として一般化可能で妥当性があると思います。看護の中心にあるべきは病ではなく人間なので。特に支持・教育を看護の重要な役割と定義づけていることは重要じゃないでしょうか。残念ながら看護教育では心理的支持・教育は体系だったカリキュラムが存在しません。悲しい事に看護一般的な機能を定義しつつも、精神科領域での活用が多いオレム理論。訳が酷くなければ良い本です2017/06/16
-
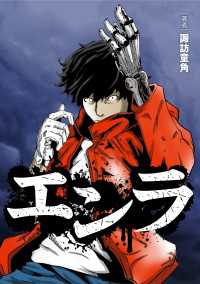
- 電子書籍
- エンラ【タテスク】 第32話 タテスク…
-
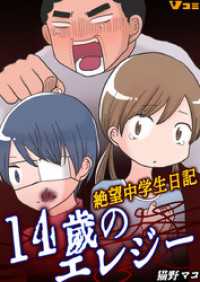
- 電子書籍
- 14歳のエレジー 絶望中学生日記102…
-
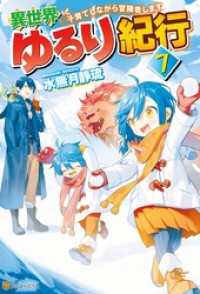
- 電子書籍
- 【SS付き】異世界ゆるり紀行 ~子育て…
-
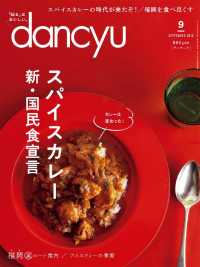
- 電子書籍
- dancyu - 2018.9月号


![REBIRTH 深宇宙への覚醒 [CDブック]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48674/4867421537.jpg)


