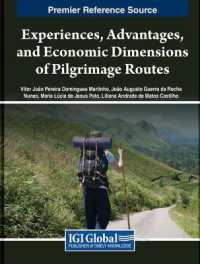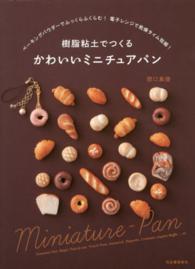出版社内容情報
病気の原因は「口呼吸」にあった!口呼吸で口内が乾いた状態が続くと、歯周病菌などの悪玉菌が増え、体全体に悪影響を与えることに。口呼吸になる仕組みを解説し、暮らしの中で鼻呼吸に改善するための方法を紹介。
●第1章 口で呼吸をしてはいけない
~病は開いた口からやってくる~口呼吸によって
起こる疾患/なぜ、口呼吸はよくないのか?/こんなときに口呼吸になりやすい/人の免疫力は口から始まる(岡崎)ほか
●第2章 呼吸の仕組みを知る
~「できて当たり前」に潜む落とし穴~
日常動作が与える影響/アリとアリ塚に見る人体システム論/生きることは"息る"こと/内呼吸と外呼吸/空気の取り込み方/鼻の構造、呼吸器の構造/口呼吸の問題に至る経緯/病気は匂いでわかる/口呼吸の歴史/嚥下に潜む落とし穴(誤嚥について)(岡崎)
●第3章 人はなぜ口呼吸になるのか
~原因は舌の位置にあった~
口呼吸になる原因/舌位置の問題/あいうべ体操で舌の位置がよくなる理由/喉から手が出る話(岡崎)/唾液について/唾液と食事の関係/睡眠の問題/睡眠態壁ほか
●第4章 暮らしの中の呼吸にまつわる疑問・対策Q&A(あいうべ体操について)
Q.継続する秘訣はあるのでしょうか?
Q.あごが痛くて口を開けないときはどうすれば?
Q.就寝前でもいいですか?
Q.子どもでもできますか?
【著者紹介】
みらいクリニック院長。1970年、鹿児島県出身。1995年、山口大学医学部卒業。山口大学医学部救急医学講座に入局後、医学部在学中より興味を持っていた東洋医学も併せて習得する。一貫して薬を使わずに体を治していく、体の使い方を変えて薬を減らしていく、といった独自の観点から治療を行っている。2006年、福岡にみらいクリニックを開業後、日本初の靴下外来を開設するなどユニークな取り組みを続けている。加圧トレーニング統括指導者、日本東洋医学会専門医、関節運動学的アプローチ(AKA博田法)医学会専門医、日本自律神経免疫治療研究会会員。著書に『薬を使わずにリウマチを治す5つのステップ』(コスモの本 2011年)、『がん治療の革命的アプローチ』(メタモル出版 2009年)、『免疫を高めて病気を治す口の体操「あいうべ」』(マキノ出版 2008年)など。
内容説明
「あいうべ体操」の考案者が教えるもっとも簡単でだれでもできる健康法。
目次
第1章 口で呼吸をしてはいけない―病は開いた口からやってくる(あなたの舌先はどこにつく?;まずは口を閉じてみよう ほか)
第2章 呼吸の仕組みを知る―「できて当たり前」に潜む落とし穴(日常動作が与える影響;アリとアリ塚に見る人体システム論 ほか)
第3章 人はなぜ口呼吸になるのか―原因は舌の位置にあった(鼻で呼吸できても油断は禁物;口を閉じるためのヒントは聖書にあった ほか)
第4章 暮らしの中の呼吸にまつわる疑問・対策Q&A20(気分をリラックスさせる、おすすめの呼吸法を教えてください。;自然とため息が出てしまうのですが、口呼吸と関係があるのでしょうか? ほか)
補考 口呼吸をやめて改善された症例―病巣感染に負けない体をつくる(病巣感染とは何か?;病巣炎症によって引き起こされる疾患 ほか)
著者等紹介
今井一彰[イマイカズアキ]
みらいクリニック院長。1970年、鹿児島県出身。1995年、山口大学医学部卒業。薬を使わずに体を治していく、体の使い方を変えて薬を減らしていく、といった独自の観点からの医療を模索し、2006年、福岡市に同クリニックを開業。日本初の靴下外来を開設するなどユニークな取り組みを続けている。加圧トレーニング統括指導者、日本東洋医学会認定漢方専門医、関節運動学的アプローチ(AKA博田法)医学会指導医
岡崎好秀[オカザキヨシヒデ]
岡山大学病院小児歯科講師(歯学博士)。1952年、大阪府出身。1978年、愛知学院大学歯学部卒業、大阪大学歯学部を経て現職。歯の治療後は子どもを笑顔で帰すこと、すなわち「子どもの心に貯金をする」ことを理念としている。日本小児歯科学会指導医、日本障害者歯科学会認定医(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
がんぞ
hashiyasume
健康平和研究所