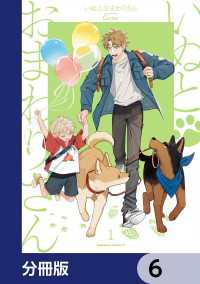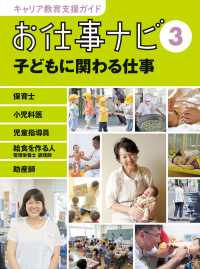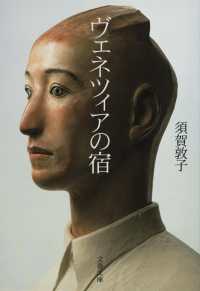出版社内容情報
第1章 ストレスの正体に迫る
子どもから大人まで、ストレスに悩む日本人
五大疾病に数えられるようになった「心の病」
ストレスにも善玉と悪玉がある
世界ではじめてストレスを定義したセリエの学説
ストレッサーの種類
ストレスを受けると起こる3つの段階
ストレスとは、ホメオスタシスを崩す力
ストレスと密接につながる自律神経系
ストレスによって体内で起きる反応プロセス
ストレスの影響は身体面・心理面・行動面に現れる
欲求は大きなストレス要因になる
ライフステージで向き合うストレスが違う
あなたのストレス度をチェック
第2章 「考え方のクセ」がストレスを生む
ストレスによる反応はすべて脳の中で起きている
「認知のゆがみ」とは何か?
「考え方のクセ」が生む感情と行動の4パターン
【ストレスパターン?@】ビクビク・オドオドする人は「不安型タイプ」
【ストレスパターン?A】イライラ・ムカムカする人は「怒り型タイプ」
【ストレスパターン?B】クヨクヨ・モンモンとする人は「うつ型タイプ」
【ストレスパターン?C】ダラダラ・ショボショボする人は「無気力型タイプ」
認知行動療法で「考え方のクセ」に気づく
第3章 うつや不安を防ぐ認知行動療法のセルフケア
あなたの「認知」を数値化してみる
「認知」と「感情」を区別する
「認知」の正体をつかむ(自動思考を下へ下へと掘り下げる)
「行動」から「認知」を変えるアプローチもできる
【認知行動療法Lesson1】感情をとらえる
【認知行動療法Lesson2】自分をほめる
【認知行動療法Lesson3】考え方をとらえる
【認知行動療法Lesson4】別の考え方をみつける
【認知行動療法Lesson5】思考変化記録表を完成させる
【認知行動療法Lesson6】変え方の3つのパターンに注意する
【認知行動療法Lesson7】行動を変える
第4章 認知行動療法から心の病を考える
病態にあわせてアプローチが変わる
心の病?@ 不眠症
心の病?A うつ病
心の病?B 社交不安症
心の病?C パニック症
心の病?D 過敏性腸症候群
心の病?E 心的外傷後ストレス障害
心の病?F 強迫症
心の病?G 拒食症・過食症(摂食障害)
心の病?H 嗜癖症(依存症)
心の病?I 肩こり・腰痛などの体の痛み
第5章 ストレスを与えない上手なコミュニケーション術
人はストレスを受ける側にも与える側にもなる
対人関係をよくする基本は、傾聴・共感・受容
アイムオッケー・ユーアーオッケーのキャッチボール
上手に自己主張する~アサーショントレーニング~
パーソナリティー障害に対応するには?
【著者紹介】
1965年、山梨県生まれ。千葉大学大学院医学研究院教授、子どものこころの発達研究センター長。精神科医。90年、千葉大学医学部卒業。プリンストン大学留学、千葉大学医学部附属病院精神神経科などを経て、現職。専門は認知行動生理学、認知行動療法など。千葉大学にて認知行動療法士トレーニングコースを主宰。著書に、『自分でできる認知行動療法 - うつと不安の克服法』(星和書店 2010年9月)、『認知行動療法のすべてがわかる本』(監修 講談社 2010年5月)、『認知行動療法セルフケアブック 職場編―考え方の悪いクセを治す』(監修 講談社 2012年12月)。
内容説明
イライラ、クヨクヨ、オドオド、無気力。心の病は、自分では気づかない認知のゆがみから起こる!
目次
第1章 ストレスの正体に迫る(子どもから大人まで、ストレスに悩む日本人;五大疾病に数えられるようになった「心の病」 ほか)
第2章 「考え方のクセ」がストレスを生む(人間特有の「ストレスをためる」という心の行動;「認知のゆがみ」とはなにか? ほか)
第3章 ストレスと上手につきあう認知行動療法のセルフケア(「認知」を数字に表してみる;確信度は柔軟に変わるもの ほか)
第4章 人にストレスを与えない上手なコミュニケーション術(対人関係をよくする基本は、傾聴・共感・受容;コミュニケーションにおけるキャッチボールの重要性 ほか)
第5章 ストレスが原因で起こる心の病(心の病は誰もがなりうる;不眠症―睡眠不足がうつや生活習慣病につながる ほか)
著者等紹介
清水栄司[シミズエイジ]
1965年、山梨県生まれ。千葉大学大学院医学研究院教授、千葉大学子どものこころの発達研究センター長。精神科医。90年、千葉大学医学部卒業。千葉大学医学部附属病院精神神経科、プリンストン大学留学等をへて、現職。専門は認知行動生理学、認知行動療法等。千葉大学にて千葉認知行動療法士トレーニングコースを主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
morinokazedayori
uniemo
のり
桃の種
KTakahashi