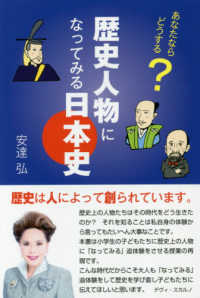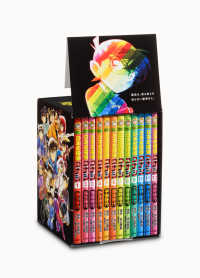出版社内容情報
林業の担い手を育てる行政支援とは?
「ウッドショック」で国産木材はどうなった?
最新データで林業の現状・しくみがよくわかる!
ロシアの輸出規制や急激な円安などの要因によって、世界の木材価格が高騰する「ウッドショック」が日本にも大きな影響を与えました。以降、国産木材が注目されるようになり、国内の林業の重要性がますます高まっています。
本書は、旧版をすべて最新データに刷新し、“森林国”日本の可能性と課題を探ります。
歴史から経営、制度、流通などの基本知識も図解を交えてわかりやすく記載。
林業のすべてを網羅した入門書です。
目次
第1章 いま林業が注目されるわけ
第2章 森林と樹木を知る
第3章 林業を知る―樹木を育てる・収穫する
第4章 林産業を知る―木材を加工・消費する
第5章 日本林業と林政の歩み
第6章 木材だけではない森林からの恵み
第7章 これからの林業の可能性と課題を知る
著者等紹介
関岡東生[セキオカハルオ]
東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科教授。専門は、森林政策学、森林教育学、森林文化論。1965年、東京都生まれ。1995年、東京農業大学大学院農学研究科林学専攻修了。博士(林学)。日本森林学会・日本環境教育学会・日本野外教育学会・日本農業教育学会・林業経済学会他に所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
16
稲作の開始とともに、平地で水が得られる農地では食料生産が行われるようになった。一方、農地には使えない産地は、建材や身の回りの道具、そしてなによりもエネルギー(薪炭)の供給地として生活に欠かせない場所であった。石炭・石油・天然ガスも、地下に凍結保存されてきた森林である。文明が原子力や風力・水力・太陽光に完全移行できるのか、それともなんらかの形で森林を真の「再生可能エネルギー」として利用するようになるのか。 まさにいまが岐路にあるようだ。2023/08/19
🍭
6
650(林業)図書館本。一般社団法人家の光協会2023年6月20日発行。林業が指す範囲がどのくらいなのか認識していなかったので興味をもって読み通してみた。内容は横断的なものでBBや植物学、植物病理学のテキストを読んだときにみたような記述が多くあった。育林、加工、流通、歴史、制度、森の活用というサブテーマ通りに進んでいくのだけれど、育林・加工・流通を知っていれば林業入門者には十分なんじゃないかと思う。正直この図書を読んでも全然林業への理解が進んだとはいえない気がするのでほかにも読むべきだね。2025/03/16
ぴよちゃん
1
県図書館 林業、森林に関すること。 中世からの里山の歴史2026/01/11
きなこ
1
分かりやすい記述で読みやすい2024/11/26