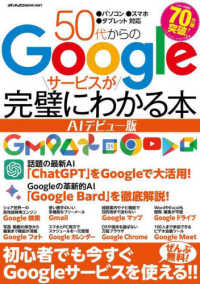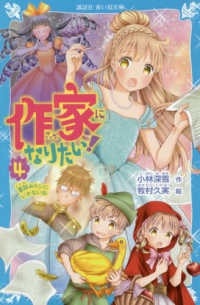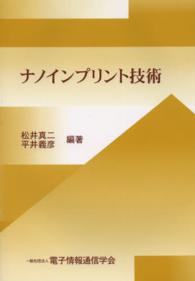出版社内容情報
畜産に関しておさえておきたい基礎知識を完全網羅! 肉・牛乳・卵など、畜産物の生産から流通、消費動向まですべてがわかる!
TPP交渉、日豪EPAの最新情報も掲載。
第1章 食べ物としての家畜・畜産物を知る
畜産・家畜とは何か?/人間はどうして畜産物を食べるのか? ほか
第2章
内容説明
食肉、鶏卵、牛乳・乳製品。この1冊で基礎知識から最新動向まで畜産のすべてがわかる。
目次
第1章 食べ物としての畜産物を知る
第2章 生き物としての家畜を知る
第3章 畜産農家の特徴と経営を知る
第4章 畜産物の流通と消費動向を知る
第5章 世界の畜産と国際貿易について知る
第6章 日本の食を支える畜産の新しい動きと可能性
著者等紹介
八木宏典[ヤギヒロノリ]
日本農業研究所客員研究員、東京大学名誉教授。1944年生まれ。1967年、東京大学農学部農業経済学科卒業。農林省農事試験場研究員、東京大学農学部助教授、教授、同大学院農学生命科学研究科教授、東京農業大学国際バイオビジネス学科教授を経て、現職。日本農業経済学会会長、日本農業経営学会会長、食料・農業・農村政策審議会会長などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
20
日本を取り巻く畜産業界の状況をわかりやすく解説。どういう経営形態があるのか、どういう飼育形態があるのかわかりやすく紹介していて勉強になった。餌は粗飼料は何とか自給できそう。トウモロコシ、麦などの濃厚飼料は牛糞を堆肥に活用すれば、作業も楽に出来そうだが、広い土地と価格競争が課題として立ちはだかる。2017/12/06
えも
17
図書館で見つけた、7月に発行されたばかりの本。「わが国の畜産の実情と課題について、分かりやすく体系的にまとめた入門書」とのことですが、畜産物、家畜、畜産農家経営、流通消費動向から国際貿易や最近の動きまで、ホントに分かりやすく新しい!しかも教科書並の知識量ですよ、これ。▼一体誰に読んでもらうといいのかなあと考えましたが、多分、正式な畜産学を学んでないけど畜産担当になっちゃった企業や行政の人にうってつけだと思いますよ、きっと。2015/09/05
ようへい
8
卵からは何か強大なアニマを感じる。例えば、日本人の年間鶏卵摂取量は337個、この数字はメキシコ人に次いで2位だ。私は卵かけご飯も好きだが、目玉焼きをご飯にのせて食べる方を好む。はま寿司に行けば必ず茶碗蒸しを注文する。生卵が半熟ゆで玉になるまでの時間は7分だ。また、鶏卵は「物価の優等生」といわれる。これは合理化を追求した「努力」の賜物に他ならない。Live Stockとは「人が食べられない野山の草を、生きた家畜の乳や肉という財産に転換し、食料として利用する営み」である。この世はまるでハンプティダンプティだ。2021/11/12
jorge70
6
世界で最初に家畜化が行われたのは1万年前で、畜種は日本ではあまり見られない山羊と羊と言われている。おとなしい性格や肉や乳、毛や皮がすべて利用できる有用性によるのだろう。旧約聖書の十戒では、蹄の割れた反芻動物は食べても良いとされ、豚などは家畜化に向いていなかったのだろう。体重1kg増やすのに必要なトウモロコシは、牛では11kgなのに対し、鶏では4kg。鶏の生産効率は高い。飼料自給率は26%であり国産の家畜も実質的な自給ではない。自給率を上げるには鶏食を推進するべきだろう。2017/06/17
Taizo
4
日本人がもっともよく口にするであろう牛豚鳥を軸に食べ方や部位の名前、飼い方、歴史、流通、ブランディング、国際貿易まで幅広く書かれた本。 普段何気なく口にしている肉がいかに様々な人の努力の結晶であるかがわかる。 驚いたのは家畜の飼料のおよそ8割を輸入に頼っているという点。食料自給率といったときにはこういった点にも注意しなければならないのだと感じた。2019/06/04