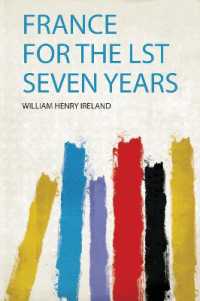出版社内容情報
英語と日本語がこれまでにたどってきた言語変化の歴史をタイポロジーの視点から捉え概説する英語と日本語の歴史的変化をタイポロジーの視点から捉える。〔内容〕日本語史概観,英語史概観,音変化,韻律論の歴史,書記体系の変遷,形態変化・語彙の変遷,統語変化,意味変化・語用論の変化,言語変化のメカニズム
第1章 日本語史概観 [清水 史]
1.1 日本語という言語
1.2 日本語史の資料
1.3 日本語史の時期区分
1.4 文字史・表記史概観
第2章 英語史概観 [児馬 修]
2.1 言語(英語)の歴史とは
2.2 英語の系統(449年以前の歴史概観)
2.3 英語史の時代区分とその根拠
2.4 古英語の資料(7世紀から11世紀の初めまで):その特徴と留意点
2.5 中英語の資料(11世紀から15世紀まで):その特徴と留意点
2.6 英語と社会(標準語と呼べるものが出現する前の不安定期)
2.7 16世紀?17世紀概観
2.8 18世紀?21世紀概観(近代後期?現代)
第3章 音変化 [服部義弘]
3.1 音変化総説
3.2 英語における音変化
3.3 日本語の音韻体系と音変化
3.4 音変化の日英対照
第4章 韻律論の歴史 [岡崎正男]
4.1 英詩の形式の変遷
4.2 古英語頭韻詩と中英語頭韻詩の形式
4.3 中英語期のさまざまな脚韻詩の形式
4.4 近代英語期以降の脚韻詩
4.5 無韻詩と自由詩における句またがり
4.6 英詩の押韻に関する問題
4.7 日本語定型詩の詩形の変遷概観
4.8 『万葉集』の詩形
4.9 『万葉集』以後の詩形
4.10 音数律の本質と詩形の内なる変化
4.11 その他の論点
第5章 書記体系の変遷 [堀田隆一]
5.1 書記言語と音声言語
5.2 書記体系の歴史
5.3 書記体系の変化
第6章 形態変化・語彙の変遷 [輿石哲哉]
6.1 本章の構成
6.2 形態・語彙に関する基本的な概念
6.3 形態論・語彙の変化
6.4 英語の形態変化・語彙の変遷
6.5 日本語の形態変化・語彙の変遷
6.6 英語と日本語の比較
第7章 統語変化 [柳田優子]
7.1 語順の変化
7.2 英語における語順の変化
7.3 日本語における語順の変化
第8章 意味変化・語用論の変化 [堀田隆一]
8.1 意味と意味変化
8.2 意味変化の類型
8.3 意味変化の要因
8.4 意味変化の仕組み
8.5 語用論の変化
第9章 言語変化のメカニズム [保坂道雄]
9.1 言語変化の要因と理論的説明
9.2 文法化現象
9.3 言語変化と言語進化
服部義弘[ハットリヨシヒロ]
著・文・その他/編集
児馬修[コマオサム]
著・文・その他/編集
目次
第1章 日本語史概観
第2章 英語史概観
第3章 音変化
第4章 韻律論の歴史
第5章 書記体系の変遷
第6章 形態変化・語彙の変遷
第7章 統語変化
第8章 意味変化・語用論の変化
第9章 言語変化のメカニズム
著者等紹介
服部義弘[ハットリヨシヒロ]
1947年愛知県に生まれる。1978年名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程中退。静岡大学名誉教授。文学修士
児馬修[コマオサム]
1951年東京都に生まれる。1976年東京教育大学大学院文学研究科修士課程修了。立正大学文学部教授。東京学芸大学名誉教授。文学修士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ishilinguist
sipsee14
-

- 電子書籍
- 理科読をはじめよう 子どものふしぎ心を…
-
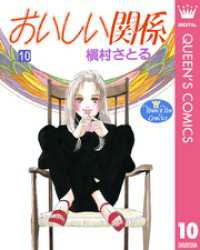
- 電子書籍
- おいしい関係 10 クイーンズコミック…