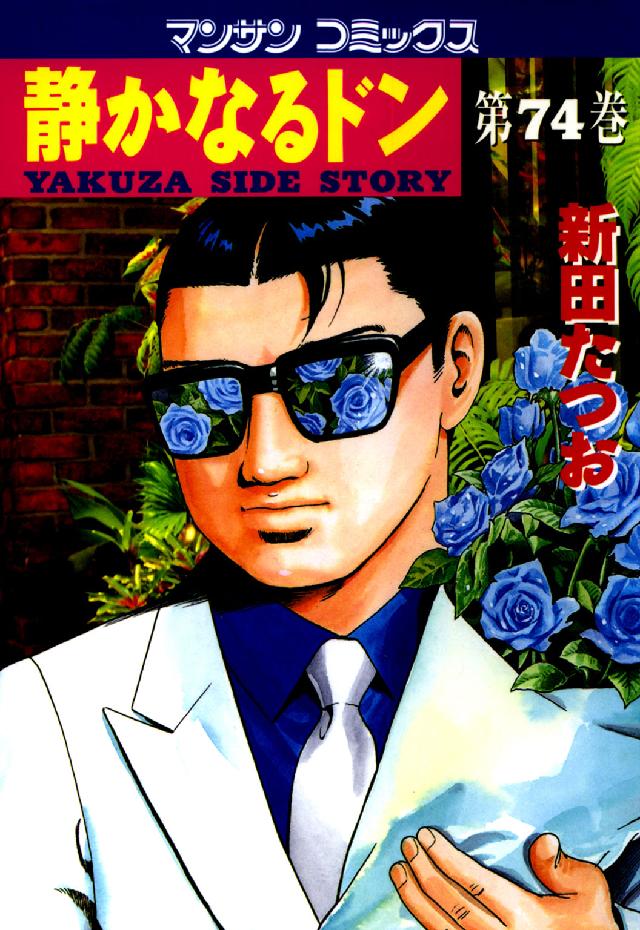出版社内容情報
「俗語」を中心に,どうして消えて行ったのか具体例を挙げながら,死語化を解説する。ことばは次々に生まれる一方で,次々に消えていく。流行語やことば遊びから生まれた語などの「俗語」を中心に,どうして消えていったのか具体例を挙げながら,歴史・社会・心理・言語・感覚との関係から死語化を解説する。
米川明彦[ヨネカワアキヒコ]
著・文・その他
内容説明
明治、大正、昭和、平成。この間に生まれ、消えていったことばを振り返り、時代の変化を見る。
目次
「スワルトバートル」―外国語もどきが消えたワケ
「テクシー」―もじりが消えたワケ
「江戸る」―「る」ことばが消えたワケ
「エンゲルスガール」―流行語が消えたワケ
「メッチェン」―若者ことばが消えたワケ
「冷コー」―老人語が消えたワケ
「電気会社の社長」―隠語が消えたワケ
「馬の爪」―業界用語が消えたワケ
「人三化七」―卑罵表現が消えたワケ
「ヘビーをかける」―外来語慣用句が消えたワケ
「隠し」―一般語が消えたワケ
「異人」―明治時代語が消えたワケ
著者等紹介
米川明彦[ヨネカワアキヒコ]
1955年生まれ。梅花女子大学教授。学術博士。専門は日本語語彙(特に俗語)・手話研究。『日本語‐手話辞典』(監修)で第17回新村出賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
matfalcon
46
明治から平成までの間に生まれたり、はやったりしたことばで、今や消えた、あるいは消えかかっていることば(主に俗語)を振り返り、時代の変化とことばの関係をさぐる。巻末に語彙索引、事項索引を掲載。2018/08/26
フリスビー
11
「流行語と流行歌は所詮はやり物。すぐに消える」、そう分かっていながら下らない言葉を真剣に研究する。こういう本は大好き。意外と明治から残っている言葉(休肝日・金欠・野次る)もあり、これらは言葉自体の完成度が高い。一方「KY」は消えたが、旧海軍ではアルファベット頭文字の隠語が使われていたし、「イルミネーション」「コスメティック」も昭和初期に使われていた。つまり歴史は繰り返す。「おなご」「ズック」「アベック」とか確かに使わないので、見ただけで笑ってしまう。でも、「じゃ、失敬するよ」と言う挨拶は粋だな、と思う。2018/06/29
kenitirokikuti
10
社会学ふうのタイトルだが、著者の専門は日本語語彙(特に俗語)であり、じっさいに俗語の大辞典など編著している。俗語は新たに生まれ、また消えてゆく/「いろいろ」をもじって「エロエロ」/江戸時代の「る」ことば。探題の動詞化、たんだえる。米澤穂信「古典部」シリーズの千反田えるってこれか! 「若気(にやけ)」→にゃける。道化→道化る(「お」がついて「おどける」)。「古典部」関係で「アイスクリーム」。氷菓なので「高利貸し(こうりがし)」、これは明治のことばで、大正ごろの女学生ことばでは「継母」を差した。2018/08/16
ふう
9
いろいろと親切に分類してあるがなぜか非常に読みにくい。横書きだからか? とにかく消えた言葉のあまりの多さに今更ながら驚く。それにしても流行語大賞の恥ずかしいことといったらもう。特に2011年の「ドドスコドドスコラブ注入」なんて表記もマヌケだしその後の諸々を思うともう泣けるw 2018/07/21
makoto018
2
図書館の本命予約本と借りた本。死語を扱う本は結構ある。「現代〈死語〉ノート」(小林信彦)のような、言葉を生んだ時代を描くエッセイもあれば、自分語りをするコラム、その変さを笑う雑文などさまざま。本作は、日本語語彙(主に俗語)を専門とする大学教授の著書。だから、まずは、消えた言葉を12パターンに分類し、明治時代から現代までの事例を挙げ、消えた理由を整理していきます。MMK(モテてモテてこまる)が海軍士官の隠語からきたとか、小林製薬(ナイシトール)の商品名が江戸時代のオランダ語もどきに似てるとか発見がたくさん。2018/07/14
-
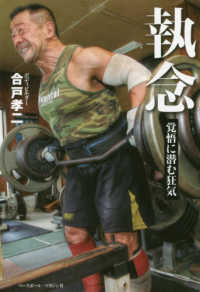
- 和書
- 執念 - 覚悟に潜む狂気


![日本旅行が考えた旅を快適にするショルダーバッグBOOK [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/42990/429906528X.jpg)