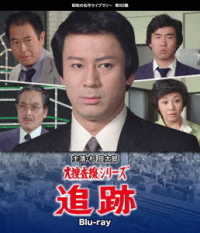目次
第1章 都市生態史:都市生活と自然との関わりの1300年(都市の歴史へのまなざし;食べものからみた都市と生態系の歴史 ほか)
第2章 都市生態系の特徴:生物多様性の観点から(都市でなぜ生物多様性を考えるのか;物理的環境の特徴 ほか)
第3章 都市における人と自然との関わり合い(都市で「人と自然との関わり合い」を考える意味;自然との関わり合いの程度を決めるもの ほか)
第4章 都市における自然の恵み(都市を洪水から守る;都市の暑さを和らげる ほか)
第5章 自然の恵みと生物多様性を活かした都市づくり(都市の自然を活かす思想と手法;都市の自然に関わる主体としくみ ほか)
著者等紹介
飯田晶子[イイダアキコ]
1983年東京都に生まれる。2012年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。現在、東京大学大学院工学系研究科特任講師。博士(工学)
曽我昌史[ソガマサシ]
1988年東京都に生まれる。2015年北海道大学大学院農学研究院博士課程修了。現在、東京大学大学院農学生命科学研究科准教授。博士(農学)
土屋一彬[ツチヤカズアキ]
1984年秋田県に生まれる。2011年東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。現在、東京大学大学院農学生命科学研究科助教。博士(農学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
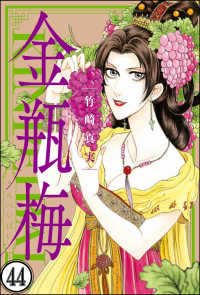
- 電子書籍
- まんがグリム童話 金瓶梅(分冊版) 【…