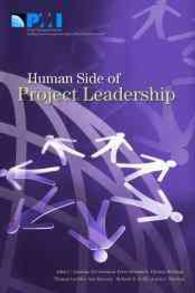目次
第1章 付着生物の多様性(付着生物の基礎;付着生物の多様性;付着生物の働き)
第2章 付着生物の幼生生態(分散機構―プランクトン幼生分散と連結性;フジツボ類の着生誘起フェロモン;付着生物の着生と光環境)
第3章 付着のしくみと付着防除技術(化学と物理からみた付着のしくみ;フジツボキプリス幼生の付着力とその測定方法;生物表面の特異な機能を模倣した付着抑制材料の開発―身の回りから海洋まで;付着阻害物質;付着生物と船底塗料の働き)
第4章 付着生物と人為的影響・環境変動(バラスト水の管理;外来付着生物・ミドリイガイの国内分布特性;環境変動と付着生物;東日本大震災と付着生物)
第5章 付着生物の利用(カキ養殖の歴史と近年の取組み;カキ幼生のAI画像検出;フジツボ類の食材利用の現状と養殖への挑戦)
著者等紹介
頼末武史[ヨリスエタケフミ]
兵庫県立大学自然・環境科学研究所。兵庫県立人と自然の博物館
室〓喬之[ムロサキタカユキ]
旭川医科大学一般教育(化学)
渡部裕美[ワタナベヒロミ]
国立研究開発法人海洋研究開発機構 超先鋭研究開発部門(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
於千代
3
分類体系ではなく、生活様式によってまとめられる「底生生物」の一部である付着生物。本書は、そんな付着生物の生態、防除、そして活用といった多角的な視点から論じた一冊。 印象に残ったのは、最後に掲載されていたフジツボへの熱量あふれるコラム。あまりの熱量に、もしかしたらフジツボってかわいいのかもしれないと思わされてしまった。2025/04/14
カコ
0
フジツボや牡蠣など、海の中でものに付着して生きる付着生物について、多角的な視点から研究のわかりやすくて面白いところを見せてくれる本。参考文献もついているのが嬉しい。2025/07/14
-

- 電子書籍
- 転生厨師の彩食記 異世界おそうざい食堂…
-

- 電子書籍
- ガラスの温室の公爵夫人【タテヨミ】第7…