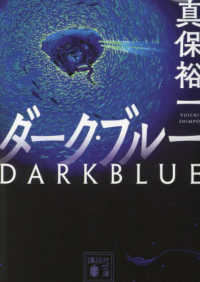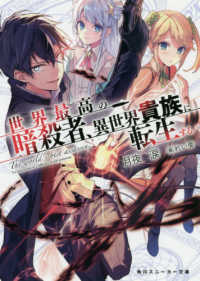目次
ヒルベルト
数学の問題
20世紀数学の新しい局面
カントル―無限に向けての数学
新しい波
数学の流れの変化
ユダヤ―流浪と迫害の歴史
ユダヤ思想
ハンガリーの新しい波―東欧におけるユダヤ系数学者
ポーランド数学―2つの大戦のはざまで
バナッハ―Scottish Cafeのつどい
バナッハ空間―解析学を蔽う広がり
20世紀前半のドイツ数学
ネーター
ワイル―数学のky章
フォン・ノイマン―無限の中の数学
ワイルとフォン・ノイマン
位相空間の誕生
位相空間の広がり
抽象を蔽う空間
位相空間上の群
抽象の中の構成
ブルバギ
トポロジーの登場
トポロジーの代数化
多様体―現代数学の場
多様体の誕生―抽象の実現
抽象数学の総合化
数学の流れについて考える
著者等紹介
志賀浩二[シガコウジ]
1930年新潟市に生まれる。1955年東京大学大学院数物系数学科修士課程修了。現在、東京工業大学名誉教授、理学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
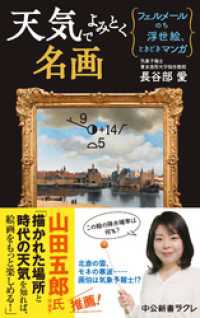
- 電子書籍
- 天気でよみとく名画 フェルメールのち浮…