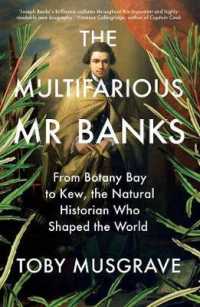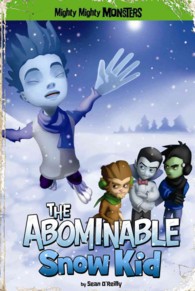出版社内容情報
カイコはどのようにして糸をはきマユをつくるのか? 脱皮のひみつ、じょうぶな糸のひみつなど、カイコの一生を探る。
小学校低学年~高学年向き
目次
まゆとさなぎ
カイコガのたんじょう
まゆをおしあけるカイコガ
羽をのばすカイコガ
とべないカイコガ
かけだしたおす
誘引腺と触角
産卵
幼虫のたんじょう
幼虫の成長〔ほか〕
著者等紹介
岸田功[キシダイサオ]
1943年、東京都新宿区に生まれる。少年時代より昆虫に興味をもち、学生時代は学業のかたわら、ガ類の研究に没頭してきた。高校生のころから昆虫の写真を撮りはじめ、以後、各種図鑑、雑誌などにすぐれた昆虫生態写真を発表している。東京都立高等学校の化学の教諭として、長く実験実習を中心とした授業を意欲的に行ってきたが、のち昆虫生態写真の撮影に専念している。日本自然科学写真協会(SSP)会員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まげりん
7
カイコだけは苦手…(⌒-⌒; )でも、4500年以上昔から家畜とは!どう家畜化していったのかそこが知りたい。2016/05/13
たまきら
4
は~かわいい…癒されるなあ。いただいた幼虫はあと1匹のこして全員まゆに。娘がさなぎを食べたがっているのがコワイ。2015/06/30
なもないのばな
3
病院ライブラリー。カイコガを飼ったことがある。近くに桑の木があってよかったと思った記憶がある。羽化したカイコガは純白で奇麗だったが、絹糸をとるためには羽化させない。人間はなんということを思いついたのだろう。それでもシルクは好きだ。お蚕さんに感謝、というのは偽善だろうか。2019/10/19
まり
0
虫で家畜って他にあるんだろうか?牛とか馬であれば野生化あるいは野良化できそうだけど、カイコはもはや自然界では生きられない。人為的に作られた共生関係なんだよね。敷きつめられた桑の葉の上の大量のカイコの写真はインパクトが大きかった。これ、世話するのキツい。慣れれば対応していけるんだろうけど。2016/02/09
ゆーいちろー
0
家に帰るとこの本が机の下にある。最近、蚕が家にやってきたので妻が買ってきたらしい。ぱらぱらとページをめくってみると、見覚えのある写真や、図版がちらほらある。なんだ、これ自分が子供の頃に持ってた本じゃないか、と気づく。今はまったくのオタク人種になってしまったが幼少のみぎりは、人並みにこういう本を面白く読んでいたのだと、懐かしく思い出す。なんせ、娯楽の少ない時代だったからね…我が子はちらりと眺めただけらしいが、親子二代に渡って同じ本に触れるのも何かの縁だろう。なんだか、これってけっこう感動的だったりする。2013/08/08