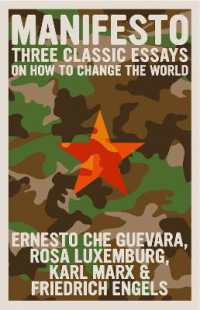内容説明
実証研究による「弥生都市」論批判!弥生文化の地域的定着から大規模集落の形成・解体にいたる過程や農業生産の様相を精微かつ広範に検証し、その社会構造の実態を解明する。
目次
第1部 弥生開始期の地域的対応と集落―縄文人と弥生人の共生(近畿における弥生時代の始まり;弥生化の具体相―河内湖周辺におけるケーススタディ;瀬戸内における弥生時代の始まり;石棒類の「なごり現象」;土偶の「なごり現象」;縄文系呪術具からみた弥生時代の始まり)
第2部 土器様相からみた弥生社会の定着(弥生時代の始まりにおける土器の地域色;遠賀川系土器の地域色の実態;朝鮮系無文土器とその影響)
第3部 弥生集落の大形化―巨大環濠集落・池上曽根からの情報発信(環濠集落を構成する要素;地形環境と集落内部の利用状況;弥生「都市」内の方形区画説は成立するのか;大形掘立柱建物・大形刳り抜き井戸とその変遷;特殊な表現をもつ建物絵画;井戸と集落;漁撈活動をめぐって;石庖丁の生産をめぐって;銅鐸鋳型と金属器生産をめぐって;BC五二年の弥生土器―年輪年代と弥生実年代、中国史書にみる倭人社会への理解;「池上曽根事件」その後)
第4部 弥生大形集落の構造とその理解(近畿における弥生「神殿」「都市」論のゆくえ;弥生中期大形集落・瓜生堂遺跡の一構成単位;「石器・木器をつくらないむら」の実際―瓜生堂遺跡における生活必需品獲得と近畿手工業生産の特質;水田経営の進展と集落)
第5部 結論(弥生大形集落の構造分析と「都市」論)
著者等紹介
秋山浩三[アキヤマコウゾウ]
1957年大阪府枚岡市額田町(現・東大阪市)生まれ。1983年岡山大学大学院修士課程(文学研究科・史学)修了。1983年(財)大阪文化財センター(アルバイト調査員)。1984年京都府向日市教育委員会(調査員のち嘱託)。1988年(財)向日市埋蔵文化財センター(技師)。1993年(財)大阪府埋蔵文化財協会(技師、のち統合などで組織名変更)。2006年博士(文学)(大阪大学)。現在、(財)大阪府文化財センター(調査部・係長)、大阪樟蔭女子大学(非常勤講師)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
![[音声DL付]やりなおし英語習慣化ドリル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0681804.jpg)
- 電子書籍
- [音声DL付]やりなおし英語習慣化ドリル