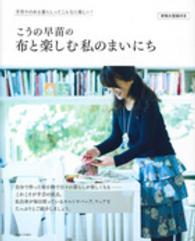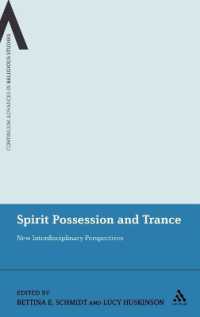感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
29
いくつもの意味でいま、アクチュアルな本。広がりがハンパない。◇中絶論争で分断が進むアメリカ人に向け、日本でどのように折り合いがつけられてきたのかその歴史をたどる。水子の祟りを悪用する存在もあるとはいえ、国家神道系の中絶禁止でもフェミニズム系の擁護でもない、庶民の仏教の供養と「沈黙」が、社会的分断を避けてきたことを紹介。それを、白黒つけるより漸進を望むプラグマティックな知恵と意義付けることで、「アメリカの伝統に合致している」と。◇格差、歴史認識…それは、Uターンして今の日本がもう一度学ぶべき姿勢ではないか。2018/01/28
おおにし
19
水子供養の起源について知りたくて読んだのですが、本書はアメリカ人の書いた学術書で、詳細すぎて通読できませんでしたが拾い読みで目的は果たせたました。日本の水子ブームのきっかけとなったのは昭和46年に建立された紫雲山地蔵寺で、住職橋本徹馬は右翼の親玉だったようです。これ以降水子供養の看板をあげるお寺が各地に広まったようです。それまでも道端のお地蔵さんが安産祈願と水子供養の両方で信仰されていたということも分かりました。2020/10/04
∃.狂茶党
10
宗教保守が中絶や避妊に罪の意識を強く強く塗り込める一方、水子供養で阿漕に儲けることは醜悪であるが、堕胎は、必ずしも貧困による苦しみの策ばかりではなく、優生学的な選別、農業林業的な発想で行われてもいたのだろうと作者は結論する。 間引き、この言葉は選別の言葉だ。2022/09/02
三柴ゆよし
7
人工妊娠中絶の賛否について、アメリカでは世論を二分するほどの大激論が戦わされている。かたや日本では、こうした問題が正面切って論じられる機会は少ないわけだが、著者によれば、中絶に関する重大な葛藤を、日本社会はすでに経験しているのだという。これまで陰惨なイメージを担わされてきた「間引き」という行為を、あくまで庶民自身の手によって選ばれた「家族計画」のひとつとして捉えなおした、極めて刺激的な論考。「水子」という問題の実相を通して、日本文化の底流を探った、読まれるべき名著である。2010/10/08
とりもり
2
アメリカ大統領選挙の論点の一つともなっていた中絶禁止を巡る議論。日本でも、為政者にとって労働力の確保という観点から表向き禁止されていたにも関わらず、近世までは「間引き」という形で庶民にとっては普通の形だった。それが「祟り」と結びつける形で水子供養としてブーム化した経緯を分析する一方で、日本人論の色彩も濃く、なかなかに興味深い。保守の価値観との親和性だったり、自民党の女性人権軽視の政策の数々がなぜ生まれるのかも、その辺に理由があるのかも。空海の蹉跌が大日如来の一神性にあったという指摘も新鮮。★★★★☆2024/11/24