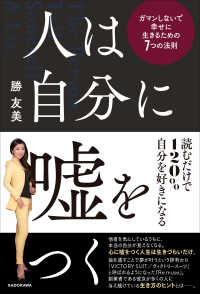内容説明
“新たなる帝国主義”はどこへ向かうのか?領土の論理とグローバル資本主義の論理、そして帝国主義的伝統―。アメリカの動静を軸に、複雑に絡み合う現代世界の歴史的・地政的動きの深層に分け入る。
目次
第1章 すべては石油のために(二つの産油会社の物語;アメリカ市民社会の内なる弁証法 ほか)
第2章 アメリカの権力はいかにして伸張したのか(領土の論理と資本の論理;ヘゲモニー ほか)
第3章 資本の呪縛(国家権力と資本の蓄積;空間経済の生産 ほか)
第4章 略奪による蓄積(消費不足か、それとも過剰蓄積か?;マルクスの逡巡 ほか)
第5章 強制への合意
著者等紹介
ハーヴェイ,デヴィッド[ハーヴェイ,デヴィッド][Harvey,David]
1935年生まれ。イギリスのオクスフォード大学、アメリカ合衆国のジョンズ・ホプキンズ大学を経て、現在、ニューヨーク市立大学大学院の人類学科教授。専門は政治経済学で、グローバルな政治・文化・経済の変遷に関する多くの著作がある
本橋哲也[モトハシテツヤ]
1955年生まれ。東京都立大学人文学部助教授。専門はポストコロニアル・スタディーズ、カルチュラル・スタディーズ
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
2
資本の蓄積はどうすれば持続可するのか? マルクスは最初の蓄積が土地の暴力的収奪としての囲い込みに始まるという(『資本論』第1巻第24章)。一方、レーニンが帝国主義にもこの囲い込みを適用する時、地理学者である著者は帝国主義を形成するにはローザ・ルクセンブルグ『資本蓄積論』の外部の包摂のほうを適当と考える。第二次大戦後の国内開発での過剰蓄積が70年代オイルショック後に変動相場制の採用以来、この動きが活発化し、国家も資本の収奪装置の一部となったからだ。本書は資本主義のポストモダンへの転換を空間と蓄積から捉える。2017/02/13
tjZero
1
21世紀に入ってからのアメリカが、新自由主義や新保守主義の名のもとに新たな帝国主義を推し進めてきたことがよくわかる1冊。グローバリゼーションによって、貯蓄は出来ないけど消費はしてくれるプチ貧乏を世界中にばらまき、そこから広く、うすく、大量に富を集積して一部の富裕層に分け与える。”おともだち”ばかりを優遇しているアベ政治もそのコビーみたい。2019/11/29
-
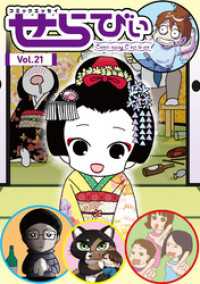
- 電子書籍
- コミックエッセイ せらびぃ Vol.2…
-
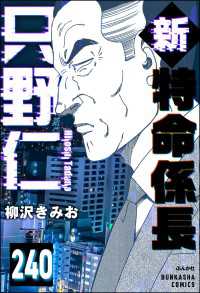
- 電子書籍
- 新特命係長 只野仁(分冊版) 【第24…