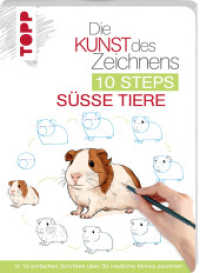内容説明
戦争遂行がすべてに優先された。その時、暮らしは、学校は…地域で発掘された事実、人びとの戦争体験、戦争遺跡から浮かび上がる戦争の実像。
目次
1章 戦争はこうして行われた(地図から消えた海岸線―東京湾要塞は首都防衛の最前線;長距離爆撃への試験飛行基地―海軍館山航空隊 ほか)
2章 人びとはこうして戦争にまきこまれた(花づくりを守った人びと―花・海藻・ウミホタルと戦争;戦争犠牲者と法号―寺院の記録からみた十五年戦争 ほか)
3章 学校と子どもたちの生活はこう変わった(「ぼくらわたしら少国民」―国民学校の子どもたち;生き残った「青い目の人形」―日米親善人形使節のゆくえ ほか)
4章 空襲下の本土決戦体制と敗戦(千葉市民を襲った「七夕空襲」―空襲をどう語りつぐか;墜落した米軍パイロットの虐殺―町民が戦犯になった ほか)
感想・レビュー
-
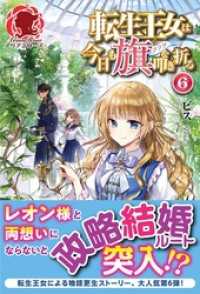
- 電子書籍
- 転生王女は今日も旗を叩き折る 6 アリ…
-
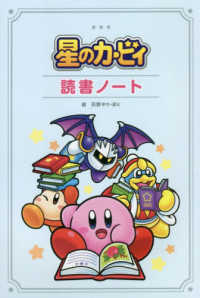
- 和書
- 星のカービィ 読書ノート