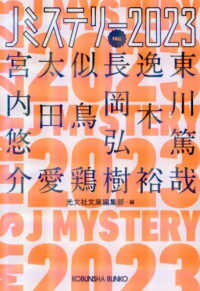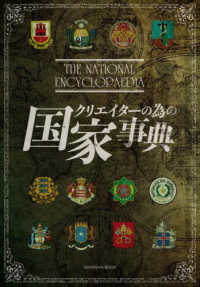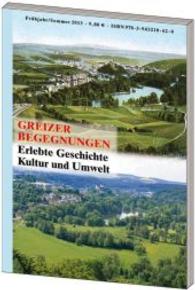内容説明
フロンティアを失ったとき、人類の進化も止まる。―人類の「幼年期」を終わらせる宇宙進化の鍵は「火星への旅立ち」が握っていた―。巨匠クラークが、自らの庭をつくるように慈しみ育て上げた「火星の地球環境化」への壮大なシミュレーション。火星こそ、私たちが還るべき未来の故郷だったのだ…。ネクスト・ミレニウムに立ち会うすべての人々への道標―科学的予測と暗示に満ちたクラーク・ワールドの最高峰。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
黄色と橙
10
何度目かの再読。SFではお馴染みの火星テラフォーミングですが、それをクラークが執筆当時最先端の科学技術と豊かな想像力を駆使して大真面目にシミュレートしたものです。初読は中学生の頃。科学的な内容は理解しきれなかったけれど、火星に広まる植物や地形の変化にワクワクし、何度も読み返した思い出の本。プラネタリウムの演目のように、どこかロマンティックな趣きもあるのはクラークならでは。火星のオリンポス山に雪が積もりそこでオリンピックが開催される…、そんな未来予想図は夢があって素敵。2012/08/18
roughfractus02
9
科学的想像力はフロンティアを必要とすると作者はいう。大気圏外に未到だった1951年に「火星の砂」で起伏のない砂地の地形として火星を想像した作者は、43年後に火星探査の歴史と共に3DCGソフトVista proを駆使して新たに火星を地球のように作り変える夢を本書で語った(1994年刊)。現時点から読めば、2年後に始まる火星無人探査計画(1996-2001)以前であり、2008年の火星有人探査という予想も実現していないが、20000mを超すオリンポス山山頂に雪が降り、生命が広がる火星の地形の描写は壮観である。2023/11/01
がんぞ
1
1969年マリナー6&7号は初めて表面に接近し写真を送ってきたが撮影された全体の1/10は、月面に似たクレーターのみの「不運にも火星でもっともつまらない部分だった」。ヴァイキングは二十数年前、地球でもっとも高いハワイ島(海中の麓から頂まで)より3倍以上高いオリンポス山、奇岩、水流の痕跡(H2Oは何処に行ったのだろう)など探究心を燃え立たせる物件の数々を明かした、著者は『火星の砂』などで示した火星の“テラフォーマナイゼーション”について語る。“保護すべき原生生物”がないことがプラスにさえなるかもしれない…2016/12/20
ニッキー
0
都筑図書館2011/09/11
yooou
0
☆☆☆★★2007/06/17