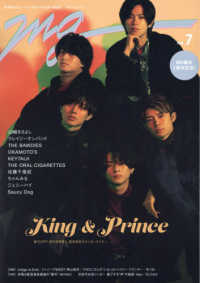目次
1 失敗事例こそ「成長のタネ」である(新卒時代の自分から手紙が来た;生徒との距離感覚を意識する;人とのかかわりの中で学ぶ ほか)
2 失敗事例から学級経営の原理を導く(「個人の正義感」だけで動いてはいけない;学級通信で失敗しないために;ギブ“アンド”テイク ほか)
3 学級経営力は教師のメタ認知能力である(学級担任には「メタ認知能力」が必要だ;「経験則」が教師を育てる;意図的に「実践」を集積・整理する ほか)
著者等紹介
堀裕嗣[ホリヒロツグ]
札幌市立向陵中学校教諭。1966年北海道湧別町生まれ。北海道立帯広柏葉高校卒業後、北海道教育大学岩見沢校入学。森田茂之に師事し国語科教育を専攻。1992年に教育研究サークル「研究集団ことのは」設立。2004年北海道教育大学札幌校・岩見沢校修士課程修了
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mori
1
失敗をどう分析するかが失敗をその後に活かすことになるのだろうと思った。中堅の先生たちの若い時の失敗談とそこから学んだことが詰まった本。ドキドキしながら読んだ。編者は「学級担任には「メタ認知能力」が必要だ」という。常に自分の考えを一歩引いて妥当かどうか考える癖をつけたいものだ。そのために実践を意図的に集積、整理する必要も合わせて述べられている。2013/08/04
s.2120
0
失敗事例の多くが行事をきっかけに荒れが表面化しているものであった。日常の学級経営のほころびが行事で子どもと多く関わり、でてくるのではないかと感じた。日常の人間関係を振り返ってみる。2013/08/22
-

- 電子書籍
- メディアの公共性 ――転換期における公…
-

- 電子書籍
- 「人体の謎」未解決ファイル