内容説明
国語科教育においても、これからの社会を生きていく子供たちが、日常生活の中で、自己の国語力をどう発揮し、どう活用していくことが望ましいかを視野に入れ、生きて働く実用的な国語力を育成することがさらに求められている。そのためには、国語科の学習で育てる資質や能力が、他教科の学習においても発揮され、総合的な学習の時間を支え、さらに、日常生活の様々な場面で実際に生きて働くかを明確にして学習指導することが必要である。本書は、日常的な評価活動を国語科授業の中に、どのように生かして機能させるかを求めた理論と実践の書である。
目次
1 高学年における日常的な評価活動の重要性と課題(日常的な評価活動を授業に生かすことの必要性;日常的な評価活動の定義と具体的な提言 ほか)
2 高学年における日常的な絶対評価活動による授業改革(絶対評価規準の方法と具体化;絶対評価を軸に相対評価を組み合わせた評価活動)
3 第五学年:評価活動を生かした授業改革事例(「話す・聞く」ことの授業実践;「書く」ことの授業実践 ほか)
4 第六学年:評価活動を生かした授業改革事例(「話す・聞く」ことの授業実践;「書く」ことの授業実践 ほか)
5 総合的な学習・他教科・家庭の学習場面等における評価活動(総合的な学習に国語科の日常的な評価活動を生かした事例;他教科等の学習に国語科の日常的な評価活動を生かした事例 ほか)
著者等紹介
瀬川栄志[セガワエイシ]
現在、中京女子大学名誉教授、全国小学校国語教育研究会名誉顧問、日本子ども文化学会会長、全創国研名誉会長、21世紀の国語教育を創る会代表。1928年鹿児島県に生まれる。東洋大学国文学科卒業。鹿児島県・埼玉県・東京都の公立学校教諭、東京都教育委員会指導主事、東京都墨田区立立花小学校・中野区立上鷺宮小学校・同鷺宮小学校長を歴任。その間、文部省教育課程教科等特別委員・教育課程調査研究協力者並びに副委員長、学習指導要領指導書作成委員、NHK学校放送教育番組企画委員。現在も全国的規模で授業理論の確立に活躍中
和田耕一[ワダコウイチ]
現在、鹿児島市立清和小学校長。九州小学校国語教育研究協議会会長、鹿児島県小学校教育研究会国語部会会長、鹿児島県作文教育研究会会長、鹿児島実践国語教育研究会会長。昭和19(1944)年鹿児島県に生まれる。鹿児島大学教育学部卒業。昭和44年より鹿児島県公立小学校教諭、昭和50年広島大学大学院に国内留学。鹿児島県東郷町立山田小学校教頭、末吉町教育委員会指導主事、山川町立山川小学校校長、鹿児島市立武岡小学校校長等歴任。国語科における生きる力・伝え合う力の育成、絶対評価の具体的な在り方等研究中
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
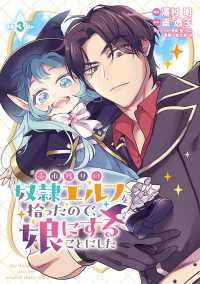
- 電子書籍
- 売れ残りの奴隷エルフを拾ったので、娘に…
-
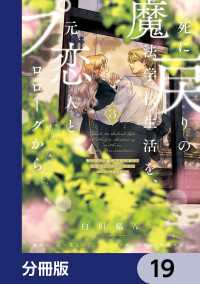
- 電子書籍
- 死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロ…
-

- 電子書籍
- 週刊GIRLS-PEDIA022 ぷに…
-
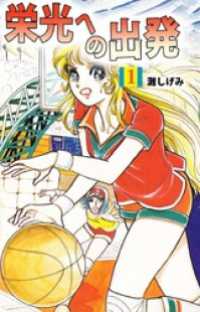
- 電子書籍
- 栄光への出発(1) まんがフリーク
-
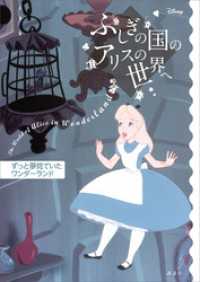
- 電子書籍
- ディズニー ふしぎの国のアリスの世界へ…



