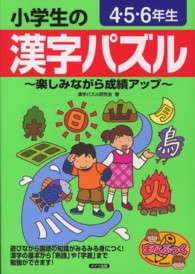出版社内容情報
授業においては、「良い発問」は様々ありますが、これだけは避けたいという「NG発問」も存在します。つけたい力や子どもの姿に違いがあっても、NG発問は共通していることが多いからこそ、それを知っておくことには意味があります。発問を学び続けるためのガイド付。
内容説明
教師は、いろいろな国語の発問モデルを自身の引き出しに持っておきたいものです。日々、教室で発問をしたり、文献や他の先生から学んだりする中で、「良い発問」の引き出しを充実させていることでしょう。それ自体はとても良いことです。ただし、その一方で気をつけたいのがNG発問の存在。つまり、この発問は避けたい、という最低限のルールがあるのです。NG発問の事例を通して、発問づくりの最低限のルールを確認しましょう。
目次
INTRODUCTION 発問ことはじめ(発問とは“問い”である;“問い”ならではの効果 ほか)
1 何を問うか(ごんぎつね―「みんな、教科書は開いたかな?」;メディアと人間社会/大切な人と深くつながるために―「わからないところはあるかな?」 ほか)
2 どう問いを並べるか(イースター島にはなぜ森林がないのか―「序論には、何が書いてあるのかな?」;スイミー―「気持ちはどう変わつていったのかな?」 ほか)
3 どう問いを発するか(ごんぎつね―「このとき、ごんはどんな気持ち?」;メディアと人間社会/大切な人と深くつながるために―「この二つの文章を比べてみると、どうかな?」 ほか)
4 どう答えを受け止めるか(サーカスのライオン―「他には?」;アップとルーズで伝える―「~ということかな?」 ほか)
著者等紹介
幸坂健太郎[コウサカケンタロウ]
北海道教育大学札幌校准教授、博士(教育学)。2015年3月、広島大学大学院教育学研究科博士課程後期課程修了。研究会「国語教師の学校」を主宰。専門は国語科教育学で、特にことばの倫理的側面、授業論に関心がある
宮本浩治[ミヤモトコウジ]
岡山大学学術研究院教育学域准教授。専門は国語科教育学で、読むことの授業論を中心にして、国語科学力論・評価論に関心がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。