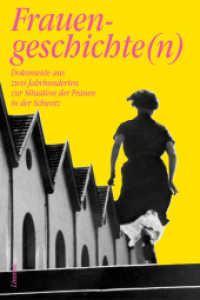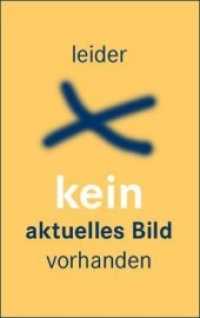目次
1 学校は社会の縮図である
2 授業で「崩壊しない学級」をつくる
3 「崩壊しない学級」づくりの手立て
4 生徒の「荒れ」をこう予防する
5 「崩壊」に立ち向かう生徒を育てる
6 やはり「学び合い」「支え合い」なのだ
著者等紹介
長野藤夫[ナガノフジオ]
TOSS中学網走みみずくの会代表。北海道留辺蕊町立温根湯中学校教頭(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ribonin
1
「崩壊させる教師」の条件に自分がことごとく当てはまっているようで、学級経営における無力感を感じた。そんな心境で読んだ「あとがき」で、この本が著者の苦体験からの視点で編著されたものであると知ったことは、私にとって励ましとなった。2013/11/01
epitaph3
1
覚悟。気概。 技術。 視線。戦術。授業力。 2009/07/23
T.E
0
崩壊する学級、崩壊しない学級。違いは1つ。担任する「教師」である。アドバルーンを徹底的に叩く。事実で、心から褒める。教育技術を身に付ける。知的な授業をする。これらの行動の根底に流れることは、「教師は学び続けなければならない」という厳然たる真理である。学ばない教師は教壇に立つ資格が無い。ちょうど脱皮しない蛇が生き残れないのと同じである。学び続けよう。どんなに細かいルールでも趣意説明が出来るような思考訓練を繰り返していこう。秩序ある学級から、自由は生まれる。学び合いは生まれる。教室を家畜小屋にしてはならない。2012/01/14
-

- 和書
- 新解釈日本国憲法