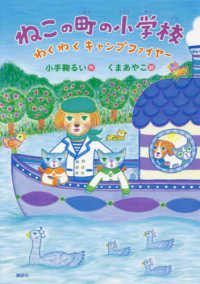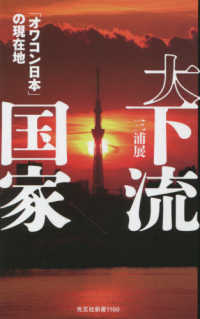内容説明
新学習指導要領で示された汎用的な「資質・能力」の育成。予測困難な時代を生きる子どもたちが真に身に付けるべき「見方・考え方」とはどうあるべきか。本書は、第三項理論が拓く新しい“読み”の地平を提案するものである。
目次
こころ
羅生門
舞姫
山月記
神様 2011
鏡
総論 第三項理論が拓く文学研究/文学教育
著者等紹介
田中実[タナカミノル]
都留文科大学名誉教授。1946年福岡県柳川市生まれ。1976年、立教大学大学院博士課程満期退学、同年私立武蔵高等学校教諭、1978年より都留文科大学国文学科に奉職
須貝千里[スガイセンリ]
山梨大学名誉教授。1950年東京都生まれ。文学研究と国語教育研究の相互乗り入れの立場から、国語教育史、文学教育論の研究に取り組む
難波博孝[ナンバヒロタカ]
広島大学大学院教育学研究科教授、博士(教育学)。1958年兵庫県姫路市生まれ。1981年に京都大学大学院言語学専攻修士課程を修了。私立報徳学園中学校・高等学校を経て、神戸大学大学院教育学研究科修士課程国語教育専攻修了。愛知県立大学を経て、現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しんえい
4
第三項理論に基づいた文学の授業が想定されている。具体的教材はこころ・羅生門・舞姫・山月記・神様2011・鏡の6つである。 第三項理論とは主体と客体の二項による世界観認識ではなく、主体と「主体が捉えた客体」と「客体そのもの」の三項で捉え直す世界観認識である。文学作品内の語り-語られる相関に了解不能の他者を浮上させる。語り手を超える機能としての語り手を把握する。還元不可能な複数性を持つ世界を認める。これらの認識の上で自己や他者、そして世界を問い続ける存在となることを教育の目的とするのが文学教育である。2019/07/12
-
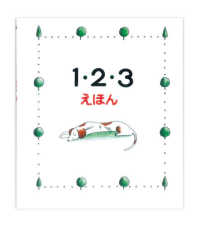
- 和書
- 1・2・3えほん