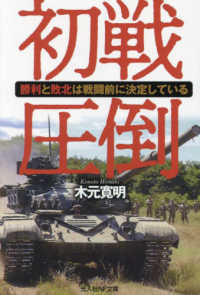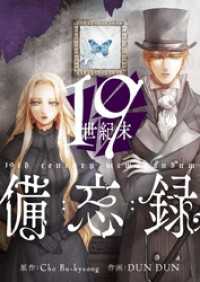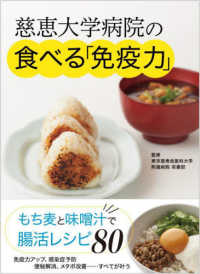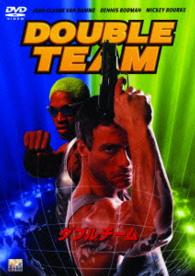内容説明
北海道から鹿児島まで全国各地の教師が、小・中学校双方から、校内研修の「日常的な最前線」を具体的に提案。通年での校内研修の取り組みに加え、喫緊の課題である生徒指導や英語学習に特化した校内での研修、子どもとの『学び合い』に活路を見出そうとする取り組みなど、通年で取り組む形とはやや違うものも、「取り組みの最前線」としてまとめられている。
目次
校内研修の「日常的な最前線」はどの辺りにあるのだろう?
カタルシスとクリエーション
「校内研修=モチベーションが高まる」に向けて、はじめの一歩
ワークショップ型のレポート検討中心に学習集団づくりプランを完成させていく研修計画
ワークショップ型職員研修で、話し合う学校風土をつくる
授業力アップで子どもを伸ばす校内研究へ
子どもと学び合う授業研究―児童参加型協議会の実践
粘り強いコミュニケーションで生まれる共通理解
同僚から学び、校外講師の飛び込み授業から学ぶ
「研修の日常化」を目指した校内研修のあり方
「ワークショップ疲れ」を意識する―“ねらい”と“状況”を分析した場づくり
自らの学びを再構成する場としての校内研修
著者等紹介
石川晋[イシカワシン]
1967年生まれ。北海道旭川市出身。1989年北海道教育大学旭川校卒業。2003年同修士課程修了。2009年河東郡上士幌町立上士幌中学校赴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
epitaph3
4
再読。次年度の研究の形作りに。中身は見えてきたが、取り組み方を模索している。2016/01/23
の
3
具体的な研修の年間計画もあって、分かりやすかった。2015/04/09
epitaph3
2
2015年159冊目。校内研修担当の教師は読んだほうがいいよ、ホント。1000円程度で手に入る情報じゃないよ。2015/03/29
mori
2
みんなが当事者意識をもって参加できる校内研修にしたいと思っているけれどなかなか難しい現状。ワークショップ型は話しやすいし、自分の意見を取り上げてもらった感がある。ならば、WS型にすればいいかというとデメリットもあるわけで…全国のいろいろな先生方の実践している校内研修を知り、自分のところなら…と考えるヒントになる書。2014/03/15
epitaph3
1
2015年19冊目。こんな薄い本で、「小さいプリンだな」と思ったとしたら、中身は濃厚でまろやかな味がする「予想外の味わいのプリン」だったという感じの本。78ページしかないのに、読み切るのに4時間近くかかっている。きっと考えて読むからなんだ。校内研修で悩んでいる先生方、ちらりとめくってみたらいかが?たぶん「やったことない研修だな」「やれたらいいな」「でもできるかなあ」という思考になると思う。「やってみないとわからない」「考えてみないとわからない」ああ、濃厚な世界。2015/01/09