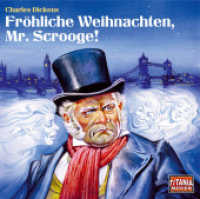目次
第1章 授業目標を考えるツボ―キャリア発達を意味づける(人は一生発達し続ける;人はこの世で果たすべき役割をもって生まれてくる ほか)
第2章 授業計画を考えるツボ―キャリア発達を方向づける(「何を」「なぜ」の視点で見直そう;「気づく」「悩む」「考える」の視点で見直そう ほか)
第3章 授業内容を考えるツボ―キャリア発達を位置づける(キャリア発達を支援する「国語」の授業;キャリア発達を支援する「算数」「数学」の授業 ほか)
第4章 授業評価を考えるツボ―キャリア発達を価値づける(キャリア発達を自覚する;キャリア発達を評価する ほか)
著者等紹介
渡邉昭宏[ワタナベアキヒロ]
1955年、東京生まれ。中央大学商学部卒業後、神奈川県立平塚盲学校、県立伊勢原養護学校、横浜国立大学附属養護学校、川崎市立田島養護学校、県立武山養護学校、県立みどり養護学校教頭を経て県立金沢養護学校副校長。2013年3月、後進に道を譲り退職。35年間特別支援教育に携わり、うち10年間進路専任に従事。第61回読売教育賞において特別支援教育部門最優秀賞。日本リハビリテーション連携科学学会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さなごん
10
ライフキャリアについて教科ではどう学ぶか。実技系教科もあって目から鱗。まずは身近なところから取り入れてみたい。2018/07/25
epitaph3
3
2015年236冊目。中教審では「基礎的・汎用的能力」が「4領域・8能力」に変わって出てきている。しかし、これは、4領域を結構統合したものであって、教科をキャリア教育で考えるには、4領域の方が考えやすいと思う。特別支援教育において、知的障害が重い子にとっても、キャリア教育を考えることができる本。しかも、教科別にもとらえるヒントをくれるのがこちら。柔軟に「情報活用能力」「将来設計能力」「人間関係形成能力」「意思決定能力」をとらえて、生徒の姿をイメージし、授業を考える。それでいいのだ。2015/05/06
hana✻マインドサポーター✻
2
10年前に出た本ですが、今こそ読みたい本だな、と。作業学習のねらいが教科学習から離れてしまうことが現場では多く(というか、教科のねらいをむりやり後付けしている)、大いに反省した。教育とは、生きていくための力を育むこと。知識や経験を積むのはもちろんだが、それは将来どう役立ちそうなのかを考えながら指導をしていきたい。ちなみにこの本、家庭での子育てにも役立つヒントがいっぱいです。2024/10/05
らら
2
授業では、教科を学ぶ(教科の知識・技能)のみでなく、教科で何を学ぶかという2つの視点が大切だと思いながらもモヤッとしていたところ、ぴったりの本だった。「『何を』『なぜ』その教科、学部で学ぶのか」それを考える視点が明確に示されていた。同じ教材を扱っても、これらのことを意識するのとしないのとでは、アプローチの仕方がかなり違ってくると思う。なんとなく楽しいのではない、将来に繋がる実践がしたい。自分のものにできるよう、何度も原点に戻って考え、実践し続けられることが大切。今後も 開いて確認したい。2018/10/18


![BBM福岡ソフトバンクホークスベースボールカード 〈2025〉 [トレカ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/45832/458321801X.jpg)