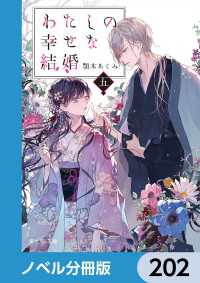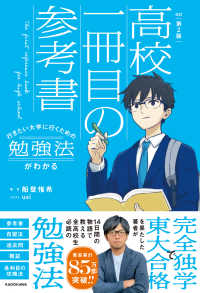内容説明
選職社会の実現という副題のもとに分析された平成11年度国民生活白書を解説したもの。各項目を質問形式で立て、図表をまじえて掲載した。企業の新しい方針、雇用状況、自己啓発、家計などの30の質問について解説。
目次
選職社会とはどのような社会ですか。
戦後続いた雇用環境が転機を迎えていると言われています。雇用環境はどのように変わりつつあるのでしょうか。
能力主義を採用する企業は、どの程度あるのでしょうか。
賃金面では能力・業績主義が広がりつつあるようですが、そうした動きを人々はどのように感じているのでしょうか。
企業の採用方法は変化してきているのでしょうか。
日本のパートタイム労働者や派遣労働者の割合は、国際的にみてどの位なのでしょうか。また、正社員になれないから仕方なくパートタイム労働や派遣労働を選ぷのでしょうか。
雇用環境の変化によって、人々の生活にはどのような変化が生じていますか。
完全失業率が高水準となっていますが、失業は、本人の所得面や精神面にどの位影響を与えるのでしょうか。
失業は本人以外にも影響を与えるのでしょうか。
高い失業率の要因として指摘される、求職者側と求人側との間におけるミスマッチはどのようなものでしょうか。
転職や再就職における、いわゆる年齢の壁はあるのでしょうか。また、それは何歳位なのでしょうか。
若い人たちの就業動向にはどのような特徴があるのでしょうか。
大学生の就職に対する意識や行動にはどのような変化がみられますか。また、企業と大学生とで採用基準についてのギャップはどのようなものでしょうか。
賃金以外にも従業員のために会社が負担している労働関係費用はどのようなものですか。また、国際的にみてそれはどの程度なのでしょうか。
人々が自己啓発に取り組む理由にはどのようなものがありますか。また、どのようなことを行っているのでしょうか。
社会入にも大学院などに通っている人はいるのでしょうか。
自己啓発にかかる費用はどの位なのでしょうか。
アメリカのコミュニティカレッジとは、どのようなものでしょうか。
コンピュータのネットワーク化など、情報化がますます進展していますが、そのような社会で必要とされる能力とはどのようなものでしょうか。
情報化に対応した専門的能力を持つことは、賃金面で利点はありますか。
アメリカでの賃金格差の拡大には、情報化の進展も影響しているのでしょうか。
家庭にも情報化が進展してきているようですが、パソコン等の情報通信関係への家計支出はどの位でしょうか。
日本における開業希望者の動向と有望な開業分野はどのようになっているのでしょうか。
パートタイム労働者や派遣労働者の雇用保険の適用状況はどのようになっていますか。
オランダの雇用政策の取り組みと、その影響はどのようなものでしょうか。
仕事に関するストレスへの対処方法はどのようにしたら良いのでしょうか。
仕事と介護は両立できるのでしょうか。
高齢世帯の消費性向はどのようなものでしょうか。
金融システム不安の発生後、家計の行動や意識は、どのように変化しているのでしょうか。
ペイオフで家計の預貯金はどの程度保護されるのでしょうか。(ぺイオフとは、預金の全額保護という特例措置が終了した後、銀行