内容説明
明和八年、道頓堀で近松半二の「妹背山婦女庭訓」は人々を熱狂の渦に巻き込む。芝居道楽が高じて絵にも義太夫節にも才を見出す者、半二の娘を頼る弟子、半二に敵わないと歌舞伎へ移った者…。操浄瑠璃に魅せられた人々の人生を喜怒哀楽豊かに生き生きと描く。直木賞&高校生直木賞W受賞『渦』に続く群像物語。
著者等紹介
大島真寿美[オオシママスミ]
1962年愛知県生まれ。92年「春の手品師」で文學界新人賞を受賞しデビュー。2011年刊行の『ピエタ』は第9回本屋大賞第3位。19年刊行の『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』で第161回直木賞、第7回高校生直木賞、第9回大阪ほんま本大賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
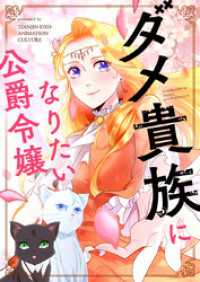
- 電子書籍
- ダメ貴族になりたい公爵令嬢【タテヨミ】…
-
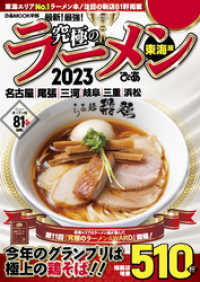
- 電子書籍
- 究極のラーメン2023東海版






