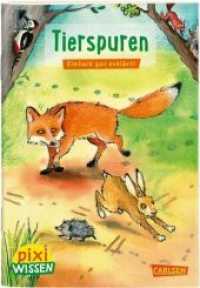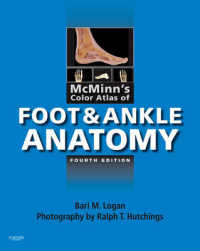出版社内容情報
牛、馬、猪、鹿、鴨、鳩、鯨、羊、すっぽん、内臓……
「人はなぜ肉を食べるのか」
問いを掲げた平松さんは、日本全国十か所をめぐり、十種の「肉」と
人とのかかわりを徹底取材。ひとつの文化として肉をめぐる諸相をとらえ、
動物とその肉について、見て、聞いて、食べて、深くその根源を考えた
前代未聞のルポルタージュ。
胸骨の端にそっと指を入れて横隔膜といっしょに引き上げると、紫色に光る
かたまりがぽろんと現れた。 (中略)ぷりっぷりのレバーの一片をそっと口の
なかに入れた。(本文 4章「鳩」より)
「生きもの」が「食べもの」になるまでの間には実に様々な工夫や技術が介在し、
「うまい肉はつくられる」ことがわかる。
信念を貫き、魅力的な多くの日本人の「仕事」の
歴史にも光を当てたエキサイティングな傑作ノンフィクション。
解説 角幡唯介
内容説明
牛、馬、猪、鹿、鴨、鳩、鯨、羊、鼈、内臓。人はなぜ肉を食べるのだろう―日本各地の「うまい肉」を作り出す人に会いに行き、「命が食べものに変わる」過程を見て聞いて、食べて、深く考える。土地に根ざした知恵と工夫、長い歴史を通じて人と獣の間に培われてきた親密な関係性に光を当てた傑作ノンフィクション。
目次
1章 羊―北海道・白糠 羊男たち一万年のロマン
2章 猪―島根・美郷町 害獣を恵みに変える挑戦
3章 鹿―埼玉~山梨・奥秩父 鹿を狩る
4章 鳩―東京・門前仲町「肉にも旬がある」
5章 鴨―石川・加賀 江戸伝来「坂網猟」を引き継ぐ
6章 牛―北海道・襟裳岬 短角牛とともに生きる
7章 内臓―東京・品川「うまい」をつくり出す現場
8章 馬―熊本 馬肉文化を守り抜く
9章 すっぽん―静岡・舞阪「露地養殖」が育む異界の味
10章 鯨―千葉・和田浦 ツチ鯨漁の現在
著者等紹介
平松洋子[ヒラマツヨウコ]
作家、エッセイスト。岡山県倉敷市生まれ。東京女子大学文理学部社会学科卒業。食文化と暮らしをテーマに執筆活動を行う。『買えない味』で第16回Bunkamuraドゥマゴ文学賞、『野蛮な読書』で第28回講談社エッセイ賞、『父のビスコ』で第73回読売文学賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Shoji
マカロニ マカロン
トムトム
こぺたろう
niz001