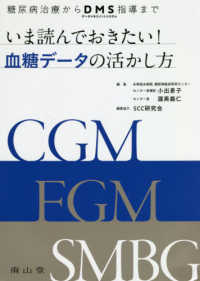内容説明
廃寺のコケの上に置かれた赤ん坊「なにか」。「ええ声」を持つ彼は、ある夫婦に引き取られ「オニちゃん」と呼ばれて成長する。ある時、その特別な声を否定され、いつしか「悪声」となっていく―。迸るイメージ、疾走するストーリー。まっさらな姿勢で見たまま感じたままを連ね、河合隼雄物語賞を受賞した力作長篇。
著者等紹介
いしいしんじ[イシイシンジ]
1966年大阪生まれ。京都大学文学部仏文学科卒。96年に短篇集『とーきょーいしいあるき』(のち『東京夜話』に改題)、2000年、初の長篇小説『ぶらんこ乗り』を出版。03年『麦ふみクーツェ』で第18回坪田譲治文学賞、12年『ある一日』で第29回織田作之助賞、16年『悪声』で第4回河合隼雄物語賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
田氏
18
いしいしんじの集大成なんじゃないかなあ、とおもう。いしいしんじというなにかが、これまで出会って見てきた声、聴いてきた景色が、色とりどりの糸となって、共感覚的に交差しながら、ひとつの大きな流れをつくる。流れをつくるからには液体であるわけで、なんならガラスのアモルファスもそのひとつに入れてもいい。液体は音を伝え、流れはあぶくを生み出す。それらは生のメタファーであるし、性でもあるし静、勢、聖、声でもある。なにかのセイが発するゆらめきが、まわりを波立たせながらひろがり、すりきれて小さくなっていくのが聴こえてくる。2021/05/21
MINA
14
十数年ぶりに著者の本読む。表現や言葉の使い方が著者独特の優しさに溢れてると感じた。読み終わって数日経つが、今でも目を閉じればお寺の前に広がる風に吹かれたコケが確かな手触りを伴って想起できる。声や音楽、一体どんなものか気になって仕方ない。2019/08/09
氷柱
6
1127作目。12月31日のみ。世に出て10年経っていない作品であることに驚く。注意深く読み進めないとすぐに訳の分からなくなる系の作品は戦前戦後の時代にこそあったけれど、こんなに直近で生み出されていたとは。普通は逆であることが多いのだけれど。、ひとつひとつの描写に力が入っていて、その描写をストーリーがギリギリつなぎとめてくれているような印象を受ける。2024/12/31
picopico
3
小説だけど描かれてるのは文字ではない。ことば、声、内側、外側、らせん、命の誕生をゼロから辿る旅。脳内のイメージ、感覚、五感の全てを使って感じる本。与えられるイメージは心地よいものもあれば怖さを感じるものある。無慈悲なこともある。かなし、かなし、かなし。気がついたら涙が出てきたりする。よい本に出会った。読むのに半年かかったけど。2020/04/05
mngsht
2
第三章の盛り上がりっぷりから、これがクライマックスでもおかしくないな〜と思って読み進めたが、そこから第四章で話が締めくくられるまでの一転二転三転…と展開が本当に面白かった。大筋だけでなく、途中挿入される人々の記憶のあぶくにも引き込まれる。わたしたち生き物の中に組み込まれた「うた」という意識は、本作が彼の作品の中ではかなり色濃いと感じたし、本作の生に対する見方は、『麦ふみクーツェ』から感じる生そのものへの祝福ということとはまた違った見方だなと思った。感覚で話してる自覚あるので両作品すぐ読み返したい…2020/04/14
-
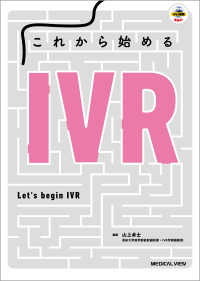
- 和書
- これから始めるIVR