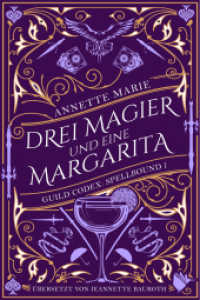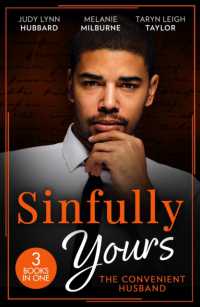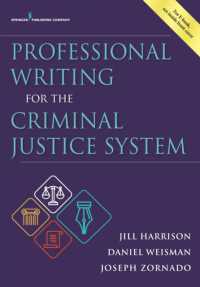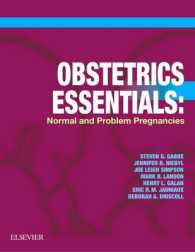出版社内容情報
中華人民共和国「内モンゴル」で生まれ、北京で文化人類学を学んだ著者は、「漢民族」が世界の中心だという中華文明の価値観に、次第に違和感を覚える。日本に留学、梅棹忠夫氏に師事。ユーラシア草原を調査するうち、従来の常識とは全く違う、価値観の逆転した中国史が形成される。それは「中国四千年の歴史」という漢民族中心の一気通巻的な歴史観からの逆転である。ユーラシア草原に勃興した様々な民族こそが「中国史」の主役であり、漢人はそのなかのひとつに過ぎない。従来、日本人は「遊牧民族たちは、豊かな中華を強奪する野蛮人である」と教えられてきた。しかし、現代の中国人がほ文明をひらいた漢民族の子孫であるというのは、実は幻想なのだ、と筆者は説く。
黄河に文明が花開いていたころ、北の草原にはまったく別個の独立した文明が存在した。北方の遊牧民と黄河の農耕民は対等の存在であり、漢人がシナを支配して「漢帝国」を称していた時代にすら、北方には別の国家が存在していた。漢人の国家が中国全土を支配していたことはなく、つねにいくつかの帝国が東ユーラシアに並立あるいは鼎立していた。その主役はスキタイ、匈奴、鮮卑、ウイグル、チベット、モンゴルといった周辺の遊牧民族である。我々が漢民族国家の代表、中国の代名詞と考える「唐」ですら、実は鮮卑の王朝である。いわゆる中華の文化が発展するのは、そうした周辺諸民族出身の王朝が世界に開かれた政策を取っていた時期であり、長城をめぐらし「壁の中に閉じこもる」のが習性の漢人によるものではないのだ。
現在の中国人は、こうした真実の歴史を覆い隠し、自分たち「漢民族」が世界の支配者であったという幻想にしがみつき、周辺民族を弾圧する。今の中国を解くキーワードは「コンプレックス」だ。正しい中国史を正視しない限り、中国は歴史に復讐されるだろう。
内容説明
「中華は漢民族の国」は幻想だ。大陸を縦横に駆け、開かれた文明を担ってきた遊牧民こそ、この地の歴史を作り上げてきた主役なのだ。南モンゴルに生まれた文化人類学者が、ユーラシアの草原の実地調査と、絶えざる批判精神で描き出したのは、日本人の中国観を逆転させる、諸民族が織り成す雄大な歴史絵巻。
目次
序章 中国の歴史を逆転してみる
第1章 「漢民族」とは何か
第2章 草原に文明は生まれた
第3章 「西のスキタイ、東の匈奴」とシナ道教
第4章 唐は「漢民族」の国家ではなかった
第5章 三つの帝国が鼎立した時代
第6章 最後のユーラシア帝国、清
終章 現在の中国は歴史に復讐される
著者等紹介
楊海英[ヨウカイエイ]
1964年、南モンゴルのオルドス高原生まれ。モンゴル名オーノス・チョクト、日本名は大野旭。北京第二外国語学院日本語学科を卒業後、日本に留学。別府大学、国立民族学博物館、総合研究大学院大学で文化人類学の研究を続ける。梅棹忠夫、松原正毅に師事し、ユーラシア草原を現地調査。2000年、日本に帰化。静岡大学人文社会科学部教授。専攻、文化人類学。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
James Hayashi
卯月
hatohebi
紫砂茶壺
Akiro OUED